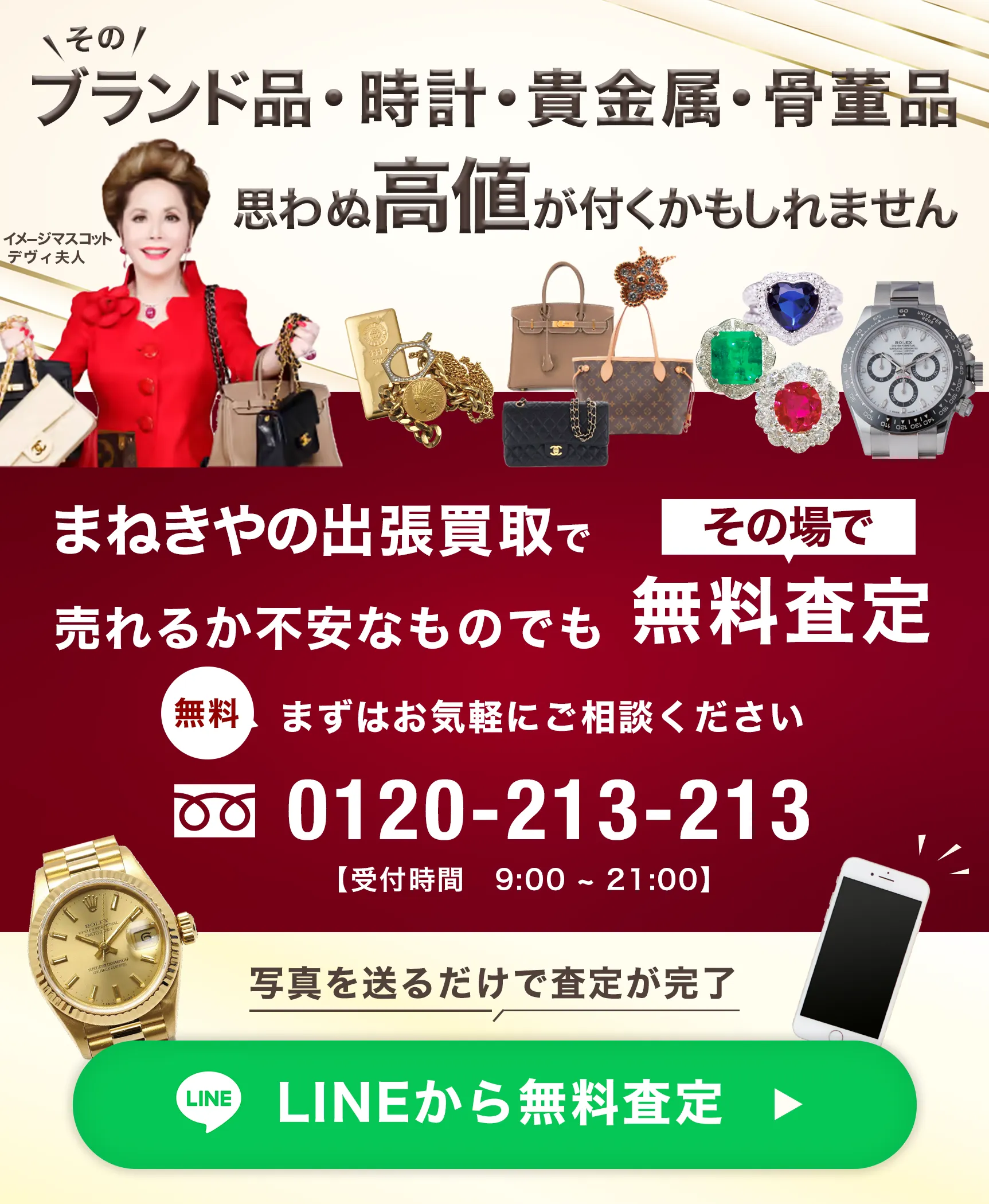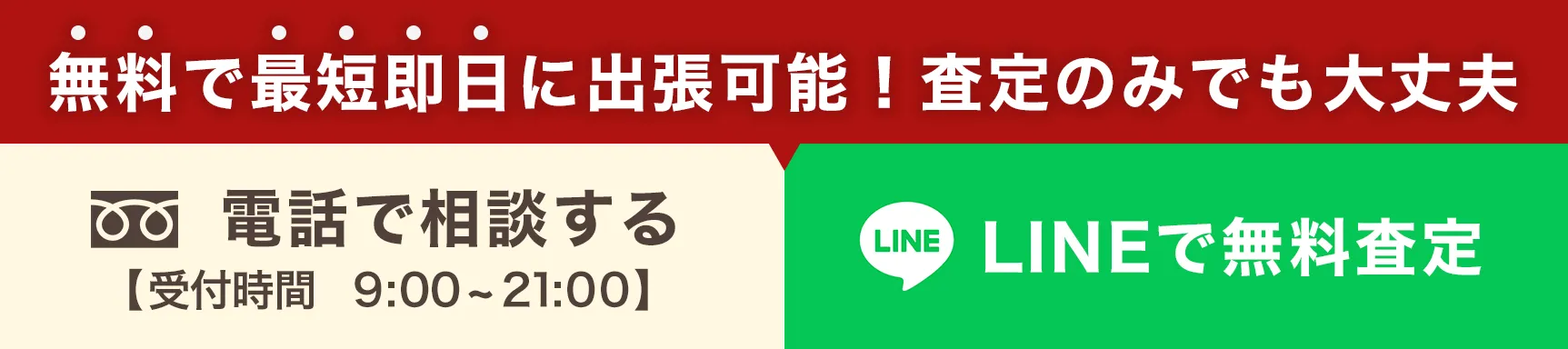着物は格によってふわさしい着用シーンが異なります。
「結婚式に招待されたけど、どのような着物を選べばいいのかわからない」
「男性と女性で着物の格はどう違うの?」
普段あまり着物を着用しない人にとって着物の格は難しく、このような悩みを抱く方が多くいます。実際、着物の格は種類や特徴が複雑で知識がなければ適切な一着を選ぶのは至難です。
実は着物の格は大きく4段階に分類でき、それぞれの特徴を知れば選びやすくなります。
結婚式や入学式、二次会のパーティーなど、TPOに合わせた着物を正しく着こなすためにも、着物の格の違いを正しく理解しましょう。
本記事では男女別で着物の格と種類の違いを説明します。着物の格を決める要素である「紋(もん)」も種類別で説明するため、ぜひ参考にしてください。
女性の着物の格の種類と見分け方

着物はTPOに合わせて使い分けるために、「格」が存在します。たとえば冠婚葬祭で身に付ける着物の種類と、近所に出かける目的で着用する着物は、シーンに合わせることがマナーです。
特に女性は着物の種類が豊富で、シーンに合わせた格は4つの段階があります。
- 正礼装:特に格が高く、婚礼や式典で着用する
- 準礼装:2番目に格が高く、婚礼の招待客やパーティーに着用する
- 略礼装:お茶会や食事会の少しかしこまったシーンに着用する
- 普段着:近所への外出や訪問など日常的に着用する
洋服でたとえると理解しやすくなります。たとえば普段着をTシャツとデニムだとすると、結婚式ではドレスなどの礼装が必要ですよね。同様の格でも、女性の場合は既婚や未婚によって着用する着物の種類が異なります。
紋の有無で同じ着物の種類の中で格の差が生まれるため、分類を理解したうえでシーンに合わせて使い分けましょう。紋は家系や地位をあらわす家紋であり、自分の持ち物であると証明する目的で着物にデザインされていました。現代では家紋を重要視しない家庭が増え、紋であればデザインは問わないシーンがほとんどです。
- 留袖(正礼装)
- 振袖(正礼装)
- 訪問着(準礼装)
- 色無地(準礼装)
- 付下げ(準礼装)
- 色無地(略礼装)
- 付下げ(略礼装)
- 鮫小紋(略礼装)
- 小紋(普段着)
- 紬(普段着)
- 浴衣(普段着)
同じ格でも着用するシーンによって、細かく分類されるため一見わかりにくく思えます。しかし、特徴を知れば誰でも簡単に見分けられますよ。
以下で女性の着物の種類別での見分け方と、着用する代表的なシーンを解説します。
1.留袖(正礼装)
留袖は既婚女性が着用する正礼装です。披露宴や結婚式での礼装の定番であり、新郎新婦の母親や祖母などの身近な親族が着用します。反対に招待された知人や友人が着用すると、マナー違反になるため注意しましょう。
留袖の中でも黒色に五つ紋が入った「黒留袖」が特に格式高く、紋は背中と両胸元、両袖の五カ所に入っています。模様なしで黒一色に染め上げた生地を使い、衿元、袖、着物を重ね合わせる部分の「おくみ」に、重ね着して見えるよう白色の布を縫い付けたデザインが特徴です。祝いの席では金や銀、白の刺繍で、鶴や花々の縁起物が描かれています。
振袖と比べて袖丈が短く、すっきりとしたシルエットが特徴です。黒留袖は招いたゲストをもてなし、礼儀を尽くす意味を持った着物だからこそ帯よりも低い下半身に模様や刺繍が施されています。
2.振袖(正礼装)
振袖は未婚女性が着る正礼装で、成人式で身に着ける着物として見かける機会が多い種類です。袖に花や動物の華やかな刺繍やプリントが施されており、成人式のほかに結納や結婚式、卒業式などの縁起がよい席で着用します。
振袖は3パターンの袖の長さがあり、袖が長くなるほど格も高くなります。
|
種類 |
袖の長さ |
着用シーン |
|
大振袖 |
三尺~三尺三寸 |
花嫁衣装 |
|
中振袖 |
二尺四寸~八寸 |
成人式 |
|
小振袖 |
二尺~二尺三寸 |
卒業式などの式典 |
知名度が高い成人式の振袖は中振袖で、手を下ろした際にふくらはぎあたりまで長さがあります。
大振袖は結婚式の婚礼衣装で、くるぶしあたりまで続く長い袖が特徴です。結婚式の大振袖は地面につくよう、足首より長さを出した「お引きずり」と呼ばれる着用方法で華やかさと高級感を演出します。
小振袖は袴と合わせた振袖で、卒業式に着る機会が多い振袖です。袖が短いため動きやすく、草履だけでなくブーツと合わせたカジュアルな着こなしも人気があります。
なお振袖は未婚の女性が着用するもので、結婚した女性は留袖に代わります。振袖の袖を短くカットして、留袖に仕立て直して着続ける人もいます。
3.訪問着(準礼装)
訪問着は柄が全体に施された準礼装の着物で、名前のとおり食事会や知人宅への訪問など、フォーマルな場からカジュアルな場まで広く対応できます。
広げて置いた着物をキャンバスのように見立てて、胸元から裾まで大きく一つのデザインを刺繍した大胆で華やかな見た目です。背中の中心に入る縫い目で模様が途切れず描かれるため、「縫い目をまたぐ模様」の意味を持った「絵羽模様」と呼びます。
一つ紋を入れた訪問着は準礼装になり、結婚式の来賓やフォーマルなパーティシーンにもふさわしい格式です。
4.色無地(準礼装)
色無地は白い生地に、黒色以外で一色に染め上げたシンプルな見た目の着物です。染色前に規則的な模様を入れた「地紋」がデザインされた着物もあり、近くで見ると模様部分が浮かび上がったように見える光沢があります。
準礼装として着用できるのは地紋入りの色無地で、結婚式やパーティーの二次会などにおすすめです。
なお、祝い事の地紋は松竹梅や鶴、亀の甲羅をイメージした六角形の亀甲など、縁起のよい「吉祥文様(きっしょうもんよう)」の使用がマナーです。
地紋が入っていない色無地は格が下がり、お出かけ着や近しい知人との茶会向けのカジュアルな着物として扱われます。
5.付下げ(準礼装)
付下げは着物の裾を中心に、細部に柄が入った控えめなデザインが特徴です。通常は外出の際の普段着として使われますが、紋が入っていると準礼装に格上げされます。紋入りの付下げであれば、結婚式の来賓やパーティー、舞台やコンクールなどの鑑賞会の改まった場で着用できます。
華やかすぎず上品な見た目のため、付下げは子どもの入学式や卒業式などの式典にもふさわしい着物です。
格式高い準礼装として身に付ける際、お祝い事であれば、吉祥文様の縁起のよい柄を選びます。帯は金箔や銀箔を使ったデザインが一般的です。
6.色無地(略礼装)
紋をつけていない色無地は、「略礼装」として使われ準礼装よりも格が下がります。白の無地の着物に、黒色以外の一色で染め上げた見た目で柄は入っていません。
近しい友人や知人同士でのカジュアルなパーティーや、食事会、お茶会の席などが主な着用シーンです。
水色やピンクの華やかな色合いの色無地はお祝い事に着用し、ダークトーンのグレーや紫などはお祝い事以外のシーンに使いやすいカラーです。
7.付下げ(略礼装)
紋が入っていない付下げは略礼装に分類され、お茶会などのカジュアルなシーンで着用されます。前述の紋入りの付下げより、低い格に分類されます。
パーティーに紋なしの付下げを着用するなら、自分が主役ではない席や友人、知人同士の気軽な会食におすすめです。付下げが生まれた背景は、戦時中に華やかなデザインの着物が禁止された歴史が関係しています。当時は着物全体に模様を入れていた訪問着が華美であるとして、模様を減らしてシンプルに仕上げた付下げが作られました。
付下げは着用した際に足元に模様が入ったデザインで、シンプルかつ上品な印象が魅力です。
華やかすぎず控えめな印象は、近所への訪問からショッピング、友だちとの食事など街中で着用する着物にも活躍します。
8.鮫小紋(略礼装)
鮫小紋は江戸小紋の一種で、鮫肌のように細かい粒で描かれたデザインの着物です。細かい粒は扇状に広がっており、まさにウロコのような見た目をしています。
鮫小紋のみでは普段着ですが、一つ紋が入ると略礼装として格が上がります。
江戸小紋は江戸時代に大名や武士が身に付ける礼服として誕生した柄の総称である一方、鮫小紋は厄除けや魔除けの意味を持つ江戸小紋の一つです。
鮫のウロコの頑丈で傷つきにくい様子にちなんで、固く身を守ってくれる縁起物として扱われてきました。
友人との集まりやパーティーなど、普段着よりも少しかしこまったスタイルの着物を選びたいときにおすすめです。
9.小紋(普段着)
小紋は全体的に同じ柄が規則的に入ったデザインの着物です。カジュアルな街歩き用からちょっとしたおしゃれ着に使われています。
|
小紋の種類 |
デザインの特徴 |
|
江戸小紋 |
鮫:鮫肌のような細かいドットで扇状に広がっているデザイン |
|
京小紋 |
京都で広まった小紋。模様が比較的大きく、複数の型紙を使って染めあげるカラフルなデザインが特徴 |
|
加賀小紋 |
京小紋の影響を受けて石川県で生まれた小紋。刺繍や金箔加工を使わない優しい雰囲気が特徴 |
小紋の格はあくまでもおしゃれな普段着で、式典やパーティーなど正装が必要な場面では着用しません。
ただし、着物の背中に一つだけ紋を入れた「一つ紋」の江戸小紋であれば、普段着から準礼装に格上げされるため入学式や結婚式でも着用できます。両袖と両胸元、背中に紋が入った五つ紋と比べると格は下がりますが、一つ紋の紬は式典だけでなくお茶会やパーティーなどのイベントにもふさわしい汎用性の高さが魅力です。
10.紬(普段着)
紬はさまざまな色の系を組み合わせて織り上げる着物です。着物が主流だった時代から、日常着として使われておりその土地の風土に合った、さまざまな紬が存在します。
たとえば、鹿児島県の奄美大島の「大島紬」は、絹糸を泥染した独特の黒色と絹の光沢で、シワになりにくく軽い着心地が特徴です。
ほかにも、山形県米沢市には特産品である紅花の汁で着物を染めた紅花染めがあります。紅花染めはやわらかいピンクの色合いが特徴で、土地ならではの紬として親しまれています。茨城県の「結城紬」は農業ができない冬の間、特産品として朝廷に献上した「あしぎぬ」から生まれた紬です。製造工程すべてを手作業で手間暇かけて作り上げるため、紬の中でも高級品に数えられています。
このように、土地ならではのさまざまな紬は普段着として各地で親しまれています。
手織りの風合いが素朴で、デザインや素材の個性を楽しめるためショッピングや友人との会食などカジュアルなシーンにおすすめです。
11.浴衣(普段着)
浴衣は夏の暑い時期に、涼しく着られるように綿で作られた昔ながらの普段着です。着物は通年着用できるよう、主に絹で作られておりつるりとした触り心地と光沢があります。
浴衣は綿のやわらかく、よく汗を吸う吸水性があり、足元も素足に下駄とカジュアルな着こなしが特徴です。
現代では夏のイベントを象徴する花火大会や夏祭りのおしゃれ着として幅広い世代に愛用されています。
また、雪が降る一月を避けて夏場に成人式がある一部地域では、振袖の代わりに浴衣で参加する人もいます。
帯やヘアアレンジなどで個性を演出でき、普段着物を身に付ける機会が少ない人でも比較的着付けが手軽な点も魅力です。
紋の種類でも格が異なる

正礼装や準礼装は、格式を高める紋が入ったデザインがほとんどです。
- 染め抜き日向紋
- 染め抜き陰紋
- 摺り込み日向紋(すりこみひなたもん)
- 縫いの陰紋
上記の紋のデザインの特徴や、主に着用されるシーンを紹介します。紋の種類の中でも、格が異なるためTPOに合わせた着こなしを心がけましょう。
1.染め抜き日向紋
染め抜き日向紋は特に格式が高い紋で、正礼装の着物に使われます。染め抜きとは模様全体を白く染め抜いたデザイン、日向紋とは白抜きされた紋を意味する言葉です。くっきり見える紋で格の高さを主張できます。
紋の大きさに詳細な決まりはありませんが、基本的に男性は約3.8センチメートル、女性は約2センチメートルです。
両袖、背中、胸元のすべてに紋が入ったデザインは「五つ紋」と呼ばれ、特に格式高く男性は喪主として喪服の第一礼装に着用します。
2.染め抜き陰紋
染め抜き陰紋は、紋を白い線で表現したデザインです。染め抜き日向紋よりも格がやや下がり準礼装に使われています。
たとえば、染め抜き日向紋は婚礼の花婿、葬儀の喪主が着用するなら、日向紋は主役ではない立場の人が選ぶ着物です。
たとえば兄弟などごく身近な親族が、染め抜き陰紋を選んで、日向紋よりも控えめな礼装として着用します。
ほかにも、正礼装では堅苦しい印象になってしまうようなパーティーシーンや、お茶会などに着用する着物でも、染め抜き陰紋が使われています。
3.摺り込み日向紋(すりこみひなたもん)
摺り込み日向紋は、紋の型紙を着物に当てて染めたデザインです。陰紋(刺繍によって紋を表現したデザイン)よりも着物の色と紋の色の差が少なく、ぼんやりと浮かび上がるような見た目です。
着物が白色に近い明るい地色の場合、前述の染め抜き紋だと紋が見えづらくなってしまいます。そこで、染め抜き日向紋よりも主張しないものの、紋のシルエットがわかる摺り込み日向紋が使われました。
摺り込み日向紋は全体となじむように、着物の柄から一色を選ぶか、地色と同系色で染める場合がほとんどです。
陰紋に次ぐ格式で、普段使いや訪問着などの日常シーンで主に着用する着物に入れられます。友人同士でのパーティーや食事会、お茶会の場面におすすめです。
4.縫いの陰紋
縫いの陰紋は刺繍によって紋を表現したデザインで、別名「刺繍紋」とも呼ばれます。染め抜きと比べて格が低く、略礼服に使われる紋です。
繊細な刺繍の手仕事で作られた紋は、独自の温かみのある風合いが魅力であり、特別感がある着物です。略礼装の中でもややカジュアルな印象があり、近所へのお出かけや友人との食事などの日常シーンで着用されています。
男性の着物の格の種類と見分け方

男性は女性とは違った紋の入り方やデザインで、格の高さの違いを出しています。
- 黒羽二重五つ紋付
- 色紋付
- お召一つ紋付
- 紬
礼装や普段着で女性の着物と似たデザインや素材もありますが、男性は格の見分け方がシンプルで比較的わかりやすいため覚えておきましょう。
以下で男性の着物の格と、格ごとの主な着用シーンを説明します。
1.黒羽二重五つ紋付
黒羽二重五つ紋付は男性の正礼装で、結婚式で新郎が着用する衣装として有名です。「黒羽二重」とは、平織りと呼ばれる経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を交互に編む手法で作られた着物で、お祝いの席でも基本黒を着用します。
名前のとおり背中、両方の袖、両胸元の合計5つに紋が入っており、素材は正絹を使って高級感を演出しています。
着物だけでなく羽織と袴を組み合わせたコーディネートが基本で、それぞれに紋が入っています。
中でも紋を白く染めた染め抜き紋は格式が高く、婚礼や授賞式など重要な式典で着用されます。
ほかにも、金や銀などの糸で刺繍した縫い紋は、染め抜き紋に続き格式高い着物です。
昔は家ごとの家紋を使っていましたが、現代では紋の種類は問わず五カ所に入っていれば正礼装として認められています。
2.色紋付
色紋付は黒以外の色地に紋が入った着物で、準礼装として着用されます。結婚式での来賓や、パーティーの二次会などフォーマルな場面にふさわしい着物です。色紋付の中でも羽二重で染め抜き五つ紋の場合、花婿の正装にも着用できます。
注意したいポイントは、花嫁が白無垢や色打掛、振袖などの正礼装であれば男性が格下になってしまう点です。
色紋付披露宴でのお色直しや二次会など、花嫁が正礼装以外を着用する際におすすめです。
五つ紋が特に格式高いですが、二次会など高い格式を求められない場面なら三つ紋でも問題ありません。
ただし色が明るすぎるとカジュアルな印象になるため、袴をダークトーンにするなど全体的に落ち着きを感じるコーディネートが求められます。
3.お召一つ紋付
お召一つ紋付は略礼装の中でも、高級感のある素材と紋で格を上げた着物です。お召とは「11代将軍の徳川家斉がお召しになられた着物」が名前の由来です。
お召は全体的に光沢がある見た目で、格式をおさえつつも上品なスタイルが求められるセミフォーマルな場面で活躍します。
またハリがあり、シワになりづらいのも特徴です。
足さばきがよく動きやすいため、パーティーや食事会などの動き回る場面や、観劇の特別なお出かけにふさわしい着物です。
4.紬
紬はさまざまな色の糸で織り上げられたカジュアルな着物です。洋服でたとえるとTシャツやポロシャツのような立ち位置で、買い物や近所の外出など日常着に適しています。
デザインも多種多様で、個性を演出できるおしゃれ着として人気があります。
普段着のためマナーもそれほど厳しくなく、インナーにTシャツやタートルネックを合わせるなど、和洋を組み合わせたアレンジも楽しめる自由度の高さが特徴です。
着物の価値を知りたければまねきやで査定してもらおう

着物の格の見分け方を男女別で紹介しました。おさえておきたい3つのポイントは次の通りです。
- 着物は正礼装・準礼装・略礼装・普段着に分けらシーンに合わせた種類を選ぶ
- 男女や地域差によっても着物の格は違う
- 紋は染め方で格の違いがありシーンや立場で使い分けられる
着物は種類による格の違いだけでなく性別や地域差もあり、価値を見極めるにはプロの鑑定が重要です。
まねきやではプロの査定士が丁寧に素材や作家、状態、柄など総合的な価値を見定めるため安心して査定をご依頼ください。
店頭買取以外にも宅配買取やLINE査定で、自宅にいながら着物の価値がわかる買取方法も用意しています。
時間がなく来店が困難な方も写真を送れば、着物の価値がLINEで判断できるため時短につながります。
着物の売却を検討している方は、まねきやに一度相談してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。

 0120-213-213
0120-213-213