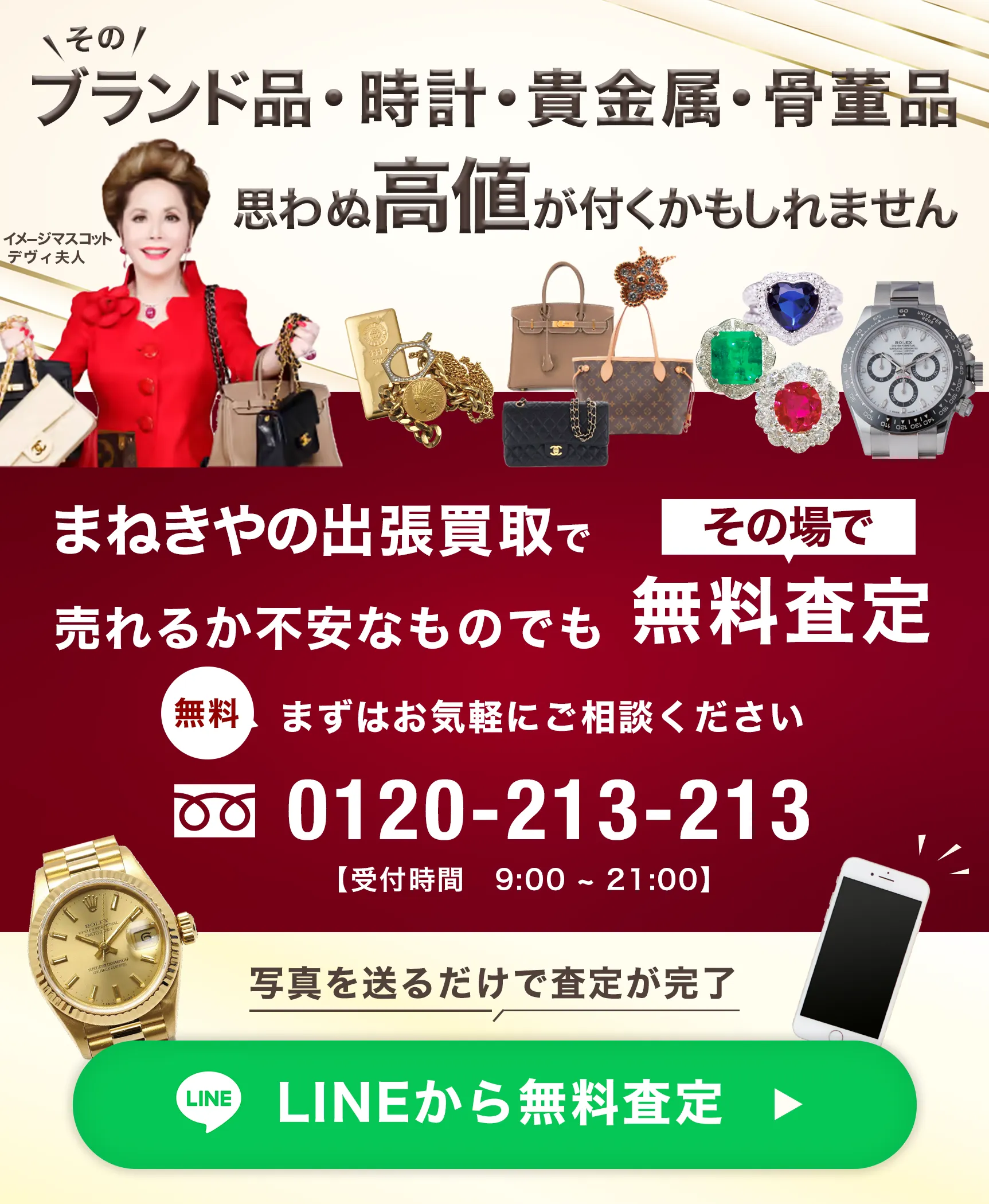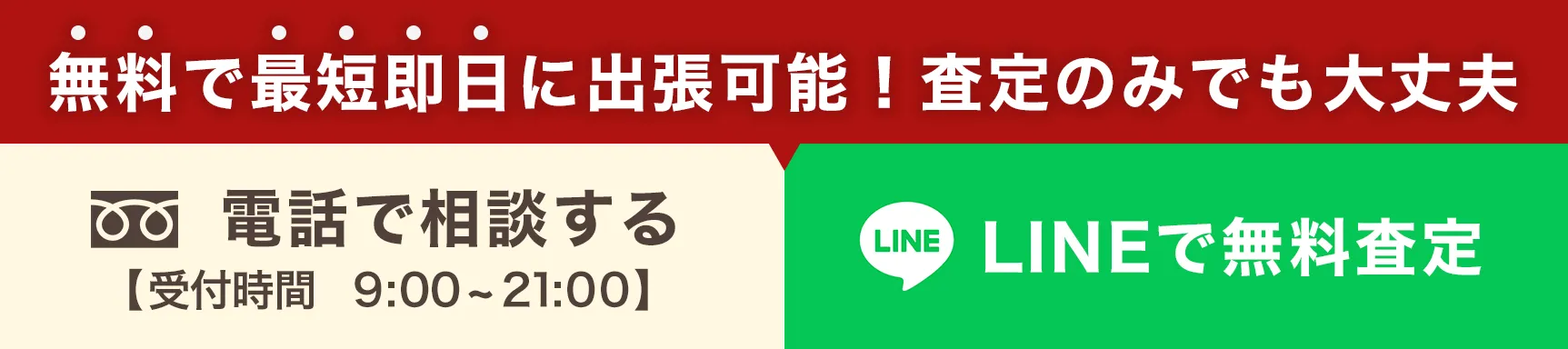大正時代のお金が現代ではどのくらい価値があるか知りたいと考えている方も多いでしょう。本記事では、大正時代に流通したお金の種類とそれぞれの現在の価値を詳しく解説します。
大正時代は1912年から1926年までのたった14年間でしたが、さまざまな種類の硬貨や紙幣が発行されました。それぞれのお金の価値は、当時と現在の物価の差や流通量によって変動し、なかには高値で買い取ってもらえるお金もあります。
本記事を参考にして、おてもとの大正時代に流通したお金がどの程度の価格で買い取ってもらえるかチェックしてみてください。
大正時代に流通していたお金

大正時代は1912年から1926年までの短い期間でしたが、第一次世界大戦や大正デモクラシーと呼ばれる民衆運動など、日本の歴史を左右する出来事がたくさん起こりました。
このような時代の流れは、当時流通していたお金の発行枚数や製造課程、金銀の含有量などにも大きな影響を及ぼし、さまざまな硬貨や紙幣が発行されることにつながります。大正時代に流通していたお金には以下のような種類があります。
- 青銅貨
- 白銅貨
- 銀貨
- 金貨
- 大正小額政府紙幣
- 大正兌換銀行券
- シベリア出兵軍票
この章では、上記の大正時代に流通したお金の具体的な解説と価値をご紹介していきます。
昔のお金の価値は保存状態だけでなく、歴史的背景や希少性などによっても変動します。それぞれのお金の詳細をチェックしてお手元の硬貨や貨幣がどの程度価値あるものか把握しましょう。
1.青銅貨

青銅貨とは、銅と錫(すず)を合成した青銅でできている大正時代の硬貨です。大正時代に流通していた青銅貨には「稲一銭青銅貨」「桐一銭青銅貨」「五厘青銅貨」の3種類があります。
|
種類 |
発行年 |
流通量 |
買取参考価格 |
|
稲一銭青銅貨 |
明治31〜大正4年 |
約4,000万〜6450万枚 |
20〜15,000円 |
|
桐一銭青銅貨 |
大正5〜昭和13年 |
約20億万以上 |
1〜10,000円 |
|
五厘青銅貨 |
大正5年〜8年 |
約4200万枚 |
5〜1,000円 |
もともと青銅貨は、明治4年(1871年)に制定された新貨条例のもと、補助貨幣として製造された「竜一銭銅貨」が主流でした。しかし、硬貨の表面にあしらわれた竜が、清(中国)の思想に基づいているとしてデザインの変更案がもちかけられ、明治31年(1898年)に旭日が描かれた「稲一銭青銅貨」が製造されました。
また大正5年(1916年)には、銅価格の変動にあわせて規格が変更された「桐一銭青銅貨」と、さらにサイズの小さな「五厘青銅貨」も作られています。それぞれの規格を見てみると、銅の価値にあわせてサイズを変えているのがわかります。
|
|
直径 |
重量 |
|
稲一銭青銅貨 |
27.87mm |
7.12g |
|
桐一銭青銅貨 |
23.03mm |
3.75g |
|
五厘青銅貨 |
18.78mm |
2.10g |
「稲一銭青銅貨」は明治33と35年、「桐一銭青銅貨」は昭和4年と5年がそれぞれ特年と呼ばれる製造枚数の少ない年にあたるため、多少のプレミア価値が付きます。しかし、それ以外の通貨は流通枚数も多いため、高い価値が付くケースは少ないです。
また「五厘青銅貨」も、明治32年に発行された5厘見本青銅貨のみプレミア価値がつきますが、それ以外は希少性が低く、買取価格もあまり高くありません。
2.白銅貨

白銅貨は、10〜30%のニッケルと銅が混ざった白銅でできている大正時代の硬貨です。大正時代の白銅貨には「大型五銭白銅貨」「小型五銭白銅貨」「十銭白銅貨」の3種類があります。
|
種類 |
発行年 |
流通量 |
買取参考価格 |
|
大型五銭白銅貨 |
大正6年 |
約8300万枚 |
50〜5,000円 |
|
小型五銭白銅貨 |
大正9年 |
約4億5800万枚 |
5〜2,000円 |
|
十銭白銅貨 |
大正9年 |
約6億6000万枚 |
100〜3,000円 |
大正時代に流通した白銅貨には「大型五銭白銅貨」「小型五銭白銅貨」「十銭白銅貨」の3種類があります。明治6年(1873年)に発行された「竜五銭銀貨」が小さすぎて不便であったことから、素材を銅に変えてサイズを大きくした「菊五銭白銅貨」と「稲五銭白銅貨」が明治22年から30年の間に製造されます。
しかし、いずれもデザインがシンプルであり偽造硬貨が出回ってしまったため、対策として大正6年(1917年)に「大型五銭白銅貨」が発行されました。裏面には八稜鏡と青海波の細かいデザインが描かれ、真ん中には4.2mmの穴が空いているのが特徴です。
大正9年(1920年)には、十銭硬貨の素材であった銀価格が高騰したため、銅を用いた「十銭白銅貨」が製造されました。「十銭白銅貨」は、同時に流通していた「大型五銭白銅貨」とデザインが類似していたため、サイズを小さくした「小型五銭白銅貨」が大正9年(1920年)に製造されます。
|
|
直径 |
重量 |
|
大型五銭白銅貨 |
20.60mm |
4.27g |
|
小型五銭白銅貨 |
19.09mm |
2.62g |
|
十銭白銅貨 |
22.12mm |
3.75g |
「大型五銭白銅貨」は大正6年、「小型五銭白銅貨」は大正9年と、発行枚数の少なかった年に製造されたものは高い値が付く傾向があります。また上記3つとも、硬貨の真ん中にある穴がずれていたり穴が空いていなかったりするエラー品の価値が高く付きやすいです。
3.銀貨

銀貨は、銀が素材となっている硬貨であり、大正時代には「新一円小型銀貨」「旭日五十銭銀貨」「旭日十銭銀貨」「八咫烏五十銭銀貨」「小型五十銭銀貨」の5つが流通していました。
|
種類 |
発行年 |
流通量 |
買取参考価格 |
|
新一円小型銀貨 |
明治20年〜大正3年 |
約1億6000万枚 |
3,500円〜30万円 |
|
旭日五十銭銀貨 |
明治39年〜大正6年 |
約1億4000万枚 |
700〜20,000円 |
|
旭日十銭銀貨 |
明治40年〜大正6年 |
約2億1000万枚 |
100〜4,000円 |
|
八咫烏五十銭銀貨 |
大正7〜8年 |
約3000万枚 |
10万〜100万円 |
|
小型五十銭銀貨 |
大正11年〜昭和13年 |
約7600万枚 |
300〜4,000円 |
「新一円小型銀貨」は1887年(明治20年)から1914年(大正3年)の間に発行されました。主に台湾銀行兌換券との引き換え基金として使用され、国内ではあまり流通しなかったため、現在でも高い価値がついています。
明治39年から大正6年にかけて製造された「旭日五十銭銀貨」と「旭日十銭銀貨」はいずれも、それまで流通していた竜の図が刻印された銀貨を廃止して新たに使用された製造された硬貨です。どちらも流通枚数が多いため、価値はあまり高くありません。
また、銀価格の高騰にあわせて製造された「小型五十銭銀貨」も同様に、流通枚数の多さから高額な値が付くケースは少ないです。ただ、大正時代の銀貨の中で最も価値の高い硬貨「八咫烏五十銭銀貨」は高額で取引される一品です。
製造予定だった大正7〜8年の間に銀の価格高騰が止まらなかったことから、市中に出回らないまま日本銀行に保管されたため、流通枚数は非常に少なく希少性が高くなっています。オークションサイトでは100万円以上の価格で落札される場合もあるほど価値の高い硬貨として知られています。
4.金貨

金貨は金が素材の硬貨であり、大正時代には「新五円金貨」「新十円金貨」「新二十円金貨」の3つが製造され流通していました。
|
種類 |
発行年 |
流通量 |
買取参考価格 |
|
新五円金貨 |
明治30年〜昭和5年 |
約130万枚 |
6万〜100万円 |
|
新十円金貨 |
明治30年〜明治43年 |
約2000万枚 |
10万〜200万円 |
|
新二十円金貨 |
明治30年〜昭和7年 |
約5000万枚 |
20万〜400万円 |
大正時代に金貨として流通していたのは「新五円金貨」「新十円金貨」「新二十円金貨」の3つです。日本は国際的な流れにあわせて、明治4年(1871年)から貨幣制度を金本位制へ移行します。
しかし、政府が保有する金が不足していたことや金そのものの価値が高かったこと、金が国外へ流出していたことなどもあり、金貨は国内ではほとんど流通していませんでした。しかし、日清戦争の賠償金として多くの金を得たため、それをもとに明治30年(1897年)に「新五円金貨」「新十円金貨」「新二十円金貨」が製造されます。
同時に新たな金平価を「1円=純金0.75g」と定めました。各硬貨の表面にはそれぞれ「二十圓」「十圓」「五圓」が刻印され、裏面は⽇章と⼋陵鏡が描かれています。各金貨の品位と重量をみると、1円=純金0.75gにおおよそ当てはまり、純金の含有量の高さから現代では骨董品や投資対象として人気です。
|
種類 |
品位(%) |
重量 |
金の重量÷平価 |
|
新五円金貨 |
金90 銅10 |
16.7 |
15.03÷0.75 |
|
新十円金貨 |
金90 銅10 |
8.33 |
7.497÷0.75 |
|
新二十円金貨 |
金90 銅10 |
4.16 |
3.744÷0.75 |
特に発行枚数の少ない年銘の金貨は価値が高く付きやすく、「新五円金貨」は昭和5年、「新十円金貨」は明治43年、「新二十円金貨」は明治6年の金貨は高値で取引されています。
5.大正小額政府紙幣

小額政府紙幣は、政府発行の補助通貨であり、大正時代には「大正小額紙幣十銭札」「大正小額紙幣二十銭札」「大正小額紙幣五十銭札」の3種類が製造されました。
|
種類 |
発行年 |
買取参考価格 |
|
大正小額紙幣十銭札 |
大正6年 |
30〜2,000円 |
|
大正小額紙幣二十銭札 |
大正6年 |
300〜5,000円 |
|
大正小額紙幣五十銭札 |
大正6年 |
100〜5,000円 |
明治から大正にかけての補助通貨には、銀貨や銅貨が用いられていました。しかし、金銀の不足によって増産が難しくなった一方で、好景気による硬貨の需要は増加したため、紙幣の「大正小額紙幣十銭札」「大正小額紙幣二十銭札」「大正小額紙幣五十銭札」が補助通貨として製造されました。
現在の日本銀行が発行するお札「日本銀行券」とは異なり、政府が臨時で発行した紙幣である点からも歴史的な貨幣であることが伺えます。現在は昭和23年に交付された小額紙幣整理法によって使用できなくなっていますが、政府発行の紙幣であり現代にはない骨董品として、未使用品は5,000円ほどの価格で買い取られるケースもあります。
6.大正兌換銀行券

大正兌換銀行券は日本銀行が発行する、いわゆる大正時代のお札です。大正時代のお札には「大正兌換銀行券1円」「大正兌換銀行券5円」「大正兌換銀行券10円」「大正兌換銀行券20円」の4種類が流通していました。
|
種類 |
発行年 |
買取参考価格 |
|
大正兌換銀行券1円 |
大正5年 |
10〜5,000円 |
|
大正兌換銀行券5円 |
大正5年 |
1,500〜20,000円 |
|
大正兌換銀行券10円 |
大正4年 |
1,000〜20,000円 |
|
大正兌換銀行券20円 |
大正6年 |
2万〜20万円 |
兌換紙幣は、お札の信用のもととなっている金や銀と交換できる価値を持つ紙幣です。金本位制を採用していた大正時代に、一定量の金銀との交換が可能な日本銀行券として大正兌換銀行券が製造されていました。
各紙幣には券面のデザインからそれぞれに以下のような通称があります。
|
種類 |
通称 |
特徴・由来 |
|
大正兌換銀行券1円 |
アラビア数字1円 |
お札の記番号が明治22年から流通していた一円札の漢数字から、アラビア数字に変更されたことに由来 |
|
大正兌換銀行券5円 |
大正武内5円、白ひげ5円 |
・券面に描かれた武内宿禰が描かれていた大正時代のお札 |
|
大正兌換銀行券10円 |
左和気10円札 |
和気清麻呂の肖像画がお札の券面の左側に描かれていたことに由来 |
|
大正兌換銀行券20円 |
横書き20円 |
券面に記載されている数字や文字が横書きだったことに由来 |
いずれも未使用品や保存状態のよい美品は数万円の価値がつく場合が多いです。なかでも、「大正兌換銀行券20円」は20円の数字がついた初めてお札だったこともあり、現在でも高値で取引されています。未使用品であれば20万円ほどの価格で買い取ってもらえる可能性もあります。
7.シベリア出兵軍票

シベリア出兵軍票は、第一次世界大戦末期の1918年から1922年にかけて行われたシベリア出兵時に使用された特別な紙幣です。
軍票とは、戦時下で国外の土地へ進行した際に、現地で物資を調達するための特別な紙幣を指します。軍票は債務として現地国に渡り、戦争終結後に発行国が支払いを保証する仕組みとなっていました。
そのため、シベリア出兵軍票は日本語とロシア語によって記載されています。
|
種類 |
買取参考価格 |
|
シベリア軍票10円 |
10万〜100万円 |
|
シベリア出兵軍票5円 |
5万〜80万円 |
|
シベリア出兵軍票1円 |
5,000円〜70,000円 |
|
シベリア軍票50銭 |
3,000〜50,000円 |
|
シベリア軍票20銭 |
2,000〜40,000円 |
|
シベリア軍票10銭 |
1,000〜20,000円 |
戦争時のみ特別に発行され、戦争が終わると政府によって回収されたため、現存する紙幣は少なく希少価値が高いです。最も高価な「シベリア軍票10円」は未使用品の場合100万円ほどの価格が付く場合もあります。
大正時代の1円は現在の440円〜1400円程度の価値がある

大正時代の1円は現在の440〜1400円ほどの価値があると言われています。大正時代のお金の価値を、戦前基準指数をベースにした大正元年と令和6年の企業物価指数から計算してみました。
|
令和6年(2025年) |
大正1年(1912年) |
価値換算 |
|
|
企業物価指数 |
913.6 |
0.646 |
約1,414倍 |
企業物価指数をもとに計算すると、大正1年の一円の価値は、令和6年の1414円と同じ価値となります。しかし、大正時代は第一次世界大戦の戦争特需により好景気を迎えたこともあり、物価の変動が激しく、大正9年(1920年)には物価が320%も上昇しました。
この場合の1円の価値も計算してみます。
|
令和6年(2025年) |
大正9年(1920年) |
価値換算 |
|
|
企業物価指数 |
913.6 |
2.0672 |
約442倍 |
大正9年(1920年)の一円の価値は、令和6年の442円と同じ価値となりました。このように、大正時代の1円の価値は各年の物価指数によって大きく変動します。また、大正時代のお金の買取価格は、希少性や保存状態によって決まり、額面価格はあくまで参考程度とした方がよいでしょう。
大正時代のお金を少しでも高価買取してもらう方法

大正時代のお金のなかでも、希少性の高いものは現代のコレクター市場でも高い人気を誇ります。しかし、同じ硬貨や紙幣でも、状態によって買取価格には大きな差が出ることもあるため、売却時には注意が必要です。
ここでは、大正時代のお金を少しでも高く買い取ってもらうためのポイントを3つご紹介します。
- 古銭買取実績が多い業者に買い取ってもらう
- 複数の買取業者を比較する
- 自分で古銭をきれいにしすぎようとしない
それぞれのポイントを押さえておくと、より高値で大正時代の紙幣や硬貨が高値で買い取ってもらえる可能性が高まります。
1.古銭買取実績が多い業者に買い取ってもらう
大正時代のお金を高く売るためには、古銭の買取実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。大正時代のお金だけでなく、江戸、明治、昭和など、さまざまな時代に流通した紙幣や硬貨を買い取っている買取業者が望ましいです。
なぜなら各時代のお金を適正価格で買い取るには、古銭の歴史的な背景や製造過程などの専門知識が欠かせないためです。さまざまな時代のお金の買取実績が豊富な業者に査定に出せば、適正価格で買い取ってもらえる可能性が高いでしょう。
また、古銭を高値で買い取ってもらうには、買取業者の再販ルートも重要です。高値で売れる再販ルートを保有している業者ほど、買取価格も高くなる傾向にあります。古銭の買取実績とあわせて、買取業者の公式ホームページをチェックしてみてください。買い取り実績や口コミなどを参考にすれば、業者の良し悪しをより正確に把握できます。
2.複数の買取業者を比較する
大正時代のお金を少しでも高価で買い取ってもらうためには、複数の買取業者の比較も大事です。同じ古銭でも業者ごとに評価基準が異なるため、査定額に大きな差が出ることがあります。
特に初めて古銭を買取へ出す方は、複数業者で相見積もりをとるようにしましょう。複数業者の見積もりを比較しなければ、買い取りに出す古銭の相場感を把握できません。
古銭の年銘、保存状態などをスマートフォンで撮影して各買取業者へ写真を送るだけで相見積もりができるサービスもあるので、まずは無料でできるところから始めてみてください。
3.自分で古銭をきれいにしすぎようとしない
古銭を売却する前に汚れを落としたくなるかもしれませんが、過度なクリーニングは逆効果になることがあります。強い薬品や研磨剤を使用してしまうと、表面を傷つけたり、価値を下げてしまう可能性があるため、基本的にはそのままの状態で査定に出すのがベストです。
特に、金貨や銀貨の場合、元々の風合いや経年変化による色合いが価値を高めることもあります。また、紙幣は破れてしまったりすると価値が大幅に落ちてしまうため、無理なクリーニングは避けるのがベストです。
どうしてもきれいにしたい場合、表面のホコリや軽く擦るだけで落ちる汚れなどを落とすのみで、それ以上のクリーニングは控えましょう。
大正時代のお金を売るならまねきやがおすすめ

本記事では大正時代のお金を高く売るコツや買い取り市場で人気の貨幣をご紹介しました。大正時代のお金のなかにも希少価値の高い種類があり、思っているよりも高値で買い取ってもらえる可能性があります。
買取に出す際はできるだけそのままの状態を維持しつつ、複数業者で相見積もりをして比較検討するのがおすすめです。もし大正時代のお金を少しでも高く売りたいなら、古銭の買取実績が豊富な「まねきや」がおすすめです。
まねきやは、専門知識を持った鑑定士が在籍しており、古銭の価値を適正に評価してくれます。ILNEを使った無料の査定サービスも行っており、スマートフォンで撮影した写真と簡単な説明文を送るだけで、最短10分でおおよその価値を診断できます。
お手元の大正時代のお金の価値を今すぐ知りたい方は、まずはお気軽にLINE査定をご利用ください。

この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。

 0120-213-213
0120-213-213