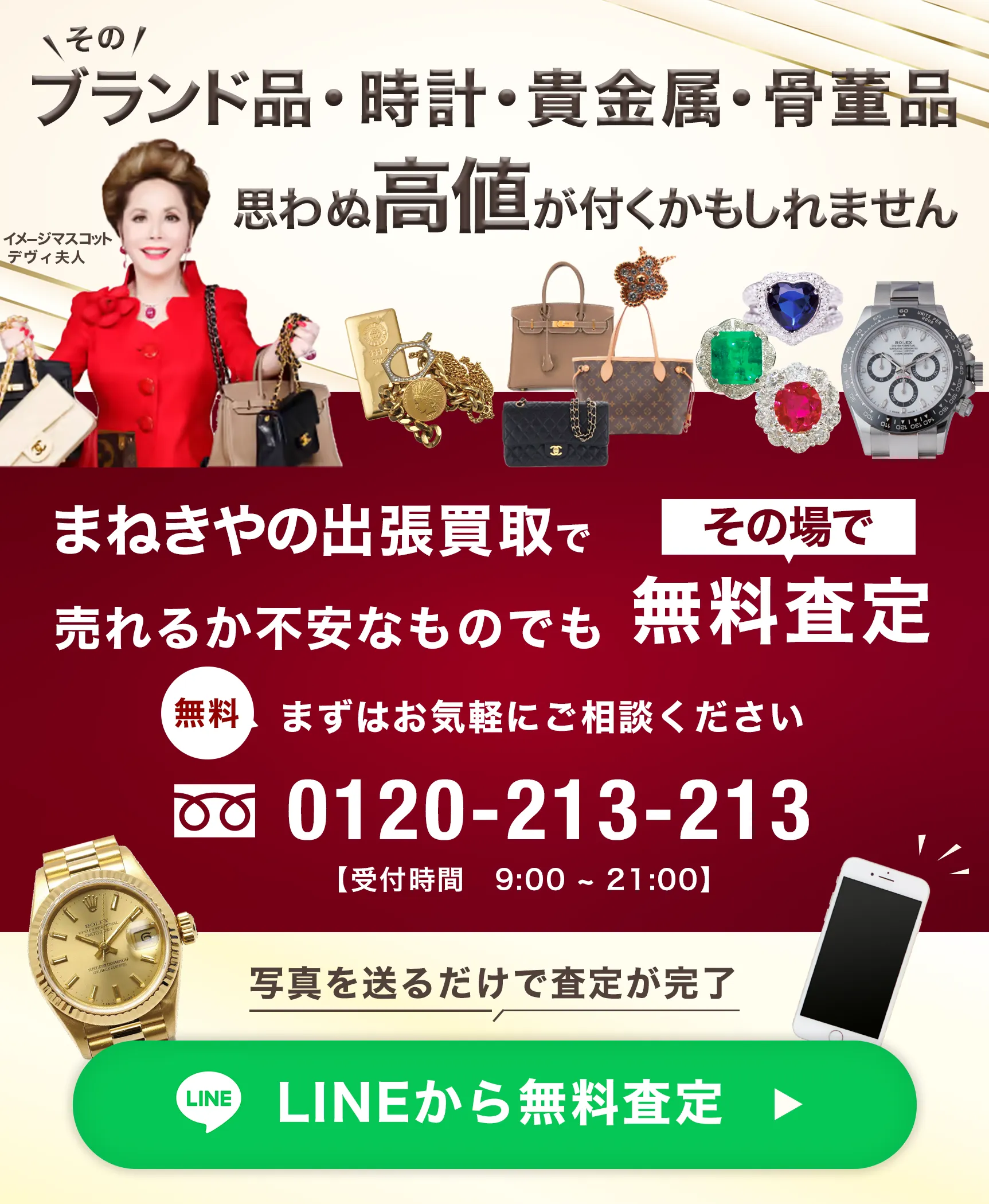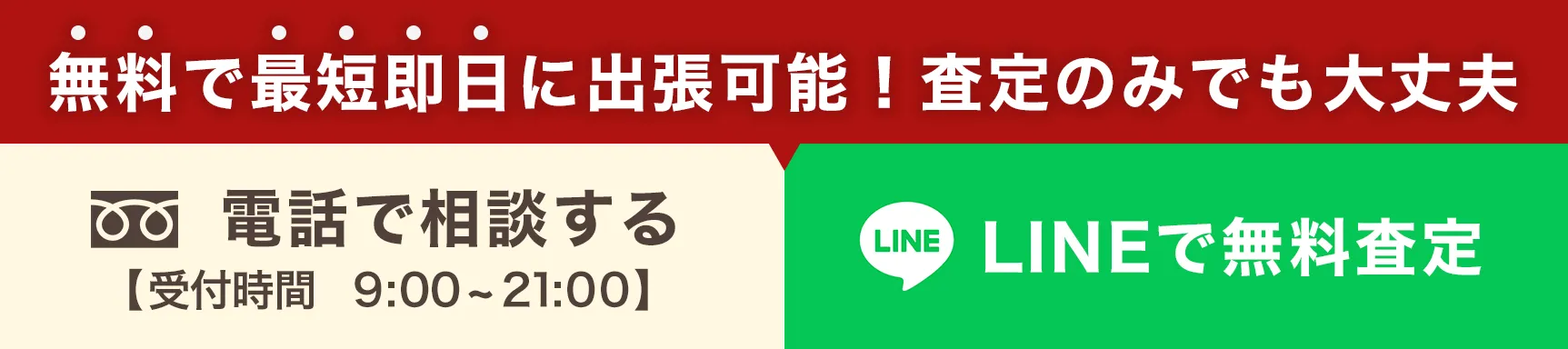リーマンショックは、ニュースを見ているとよく耳にする機会があります。 しかし、リーマンショックという言葉は知っていても、具体的な意味はわからない方も多いのではないでしょうか?
リーマンショックは、ニュースを見ているとよく耳にする機会があります。 しかし、リーマンショックという言葉は知っていても、具体的な意味はわからない方も多いのではないでしょうか?
この記事ではリーマンショックとは何か、日本への影響はどんなことがあるのかわかりやすくご説明します。 そしてリーマンショックが起きたときに、上昇する金相場の秘密をまとめています。今後金の資産運用を考えている方もぜひチェックしてください。
リーマンショックとは

リーマンショックは2008年の9月に、アメリカの投資銀行リーマンブラザーズが破綻したことで広がった世界的な金融不安のことです。
リーマンブラザーズは世界に影響を与えるほどの有力投資銀行だったため、破綻したことで株価の下落が続き、世界中を巻き込んだ同時不況を起こしたのです。
1.サブプライムローンの問題点とは
リーマンブラザーズが破綻するきっかけになったのは、サブプライムローンによる負債が大きくかかわっています。
リーマンブラザーズは低所得者向け住宅ローンのサブプライムローンの証券を販売しました。 しかし、債務者が住宅バブル終了の影響で返済できなくなってしまった結果、リーマンブラザーズは経営継続が困難な状況に。
住宅バブルが弾けた結果なんと約64兆円もの負債をかかえることになったのです。 その結果リーマンブラザーズは破綻して世界的不況を招いたと同時に、連鎖的にほかの大手金融機関の経営危機にまで発展しました。
2.リーマンショックの日本への影響とは
リーマンショックは日本にまで影響を及ぼしました。たとえば日経平均株価は、日本のバブルが弾けてしまったあとよりもさらに安値の水準を記録しました。日本の貿易最大国がアメリカであることも大きく影響し、輸出関連に携わる企業は大きな打撃を受ける結果になったのです。
その結果、日本の企業でも派遣切りが多発し社会問題に発展していきました。この影響はリーマンショックから数年続き、なんと1万5千件もの会社が倒産したとまで言われています。 さらに金融機関に対しても、ほかの大きな銀行も突然倒産するかもしれない不安から、お金を引き出す人が増え、預ける人が一気に減少しました。すると銀行そのものにお金がなくなり、企業が資金を借りることができず資金繰りに大きな問題が出たのです。
リーマンショックとその後の経済回復
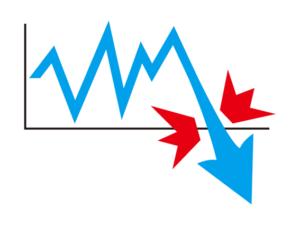
リーマンショックによる世界的な金融危機は、想像以上に長期間にわたって経済回復に時間を要しました。しかし、各国政府と中央銀行による協調した政策対応により、世界経済は段階的に安定を取り戻すことができたのです。
この回復過程で重要だったのは、従来とは規模も手法も大きく異なる金融政策の実施でした。アメリカのFRB(連邦準備制度理事会)を筆頭に、各国中央銀行は史上最大規模の量的緩和政策を導入し、金利をほぼゼロ%まで引き下げる異例の措置を取りました。同時に政府も大規模な財政出動を行い、金融機関への資本注入や雇用支援策を実施したのです。
具体的には、アメリカ政府は総額7,000億ドル規模の緊急経済安定化法を成立させ、主要金融機関の救済を行いました。また、FRBは2008年から2014年まで段階的に3回の量的緩和(QE1〜QE3)を実施し、合計で約4兆ドルもの資金を市場に供給しました。これらの政策により、金融システムの信用不安は徐々に解消され、実体経済の回復基盤が整えられたのです。
ただし、この回復過程は決して平坦ではありませんでした。政策効果が実体経済に波及するまでには相当な時間を要し、特に雇用や消費の完全な回復には約8年の歳月が必要となったことを理解しておく必要があります。
1.株価の回復までにかかった期間
株式市場の回復速度は、経済危機の深刻さとその後の政策対応の効果を測る重要な指標となります。リーマンショック後の株価回復には、アメリカと日本で大きな差が生じました。
アメリカの代表的な株価指数であるS&P500は、2007年10月の高値から約57%下落しました。その後、FRBの積極的な金融緩和政策と政府の経済対策により、2013年3月にようやく危機前の水準を回復し、完全な回復まで約4年間を要したのです。
一方、日本市場の回復はさらに長期化し、日経平均株価は2009年に7,054円まで落ち込んだ後、2007年の高値18,261円を再び上回るまでには8年程度の歳月が必要でした。
この回復期間の差は、各国の金融政策の積極性や姿勢の違いが一つの要因と考えられています。
アメリカでは迅速かつ大胆な政策対応により比較的短期間での回復を実現しましたが、日本では比較的経済状況が安定しているとの判断から慎重な政策運営をおこない、利下げは実施に踏み切りませんでした。
上記のみが回復期間の違いを説明する理由ではないものの、こういった両国の対応・姿勢の違いが株価の回復スピードに影響を及ぼしたと考えられます。
2.雇用と消費の回復状況
金融市場の回復に比べ、雇用と消費の回復はさらに時間を要する傾向がありました。雇用市において、リーマンショック後のアメリカでは失業率が危機前の5%台から2009年10月には10.0%まで急上昇し、雇用の完全回復には約6年間が必要でした。
雇用回復が遅れた背景には、企業が一度削減した人員を再雇用への慎重姿勢がありました。企業は売上回復を確認できるまで採用を控え、既存従業員の労働時間延長や生産性向上で対応する傾向が強かったのです。
消費動向でも同様の傾向が見られ、個人消費支出は2009年を底に緩やかな回復基調を辿りましたが、力強さを取り戻すまでには時間がかかりました。
住宅市場では、2006年をピークに下落し続けた住宅価格は、回復傾向に転じるまでに6年を要したほどです。
3.リーマンショック後の経済政策の変化
リーマンショックは世界の金融政策の常識を根本から変えました。とりわけ、各国中央銀行は従来の政策の枠を大幅に超えた対応を余儀なくされたため、これにより経済政策の幅が大きく広がりました。
特に大きな変化は量的緩和政策の本格導入でした。FRBは2008年11月に第1次量的緩和(QE1)を開始。住宅ローン担保証券や長期国債を大量購入し、市場に直接資金を供給する手法を取り入れました。これは従来の短期金利調整だけでは対応できない危機の深刻さを示すものでした。その後も2010年のQE2、2012年のQE3と段階的に拡大し、850億ドルの資金を市場に投入しました。
同様に欧州中央銀行(ECB)も2015年から量的緩和を開始し、日本銀行も2013年に「異次元の金融緩和」と呼ばれる大規模な政策を実施しました。
特にアメリカのFRBは、雇用の最大化と物価の安定の従来からある二つの使命を追求しつつ、ドッド・フランク法(米国金融規制改革法)によって金融監督機能が強化して金融の安定かを測りました。また、政策決定の透明性を高めるため、将来の政策方向性を事前に市場に伝える「フォワードガイダンス」という手法も積極的に活用するようになったのです。
リーマンショックと現在の経済危機との比較

リーマンショックとそれ以降に発生した経済危機は、発生原因から影響の波及経路、そして政策対応まで根本的に異なる性格を持っています。
これらの違いを理解すれば知識がつくだけでなく、資産を持っている方は経済危機への備えや投資戦略のよりよい組み立てにもつながる可能性があります。
- コロナショックとの違い
- 2022年以降のインフレ・金利上昇との関係
- 今後同様の金融危機が起こる可能性は?
それぞれのケースで、一致している部分と異なる部分を比較してみていきましょう。
1.コロナショックとの違い
リーマンショックとコロナショックは、同じ「経済危機」でありながら、その発生メカニズムと回復パターンが対照的な特徴を示しています。
特に重要な違いは、リーマンショックが金融システムの信用不安から実体経済へと波及する流れで発生したのに対し、コロナショックは感染症蔓延という外部要因による経済活動の物理的制限から始まった点です。
また、政策対応の規模と効果の違いも顕著でした。アメリカでは、リーマンショック時の緊急経済安定化法が総額7,000億ドルだったのに対し、コロナ対策では2020年度だけでおよそ6兆ドルを超える財政出動を実施しました。その結果、S&P500株価指数はリーマンショック後の回復に4年を要したのに比べ、コロナショック後はわずか5ヵ月で下げ幅を戻したのです。
2.2022年以降のインフレ・金利上昇との関係
2022年以降に世界経済を襲ったインフレの波は、リーマンショック後の経済環境とは正反対の課題を提起しています。そもそも、リーマンショック後の大きな懸念はデフレーションでしたが、2022年以降はインフレーションの制御が中心課題となったのです。
インフレ発生の根本原因を見ると、リーマンショック後のデフレ懸念とは構造がまったく異なります。
2022年のインフレは、コロナ禍による供給網の混乱、労働力不足、そしてロシアによるウクライナ侵攻にともなう資源価格の急騰が主因でした。世界の消費者物価指数は前年比7.4%となり、近年稀に見るインフレ率を記録したのです。
これに対し、例えばアメリカではリーマンショック後の2009年には一時的にデフレ状態に陥り、物価上昇率を2%まで押し上げることに苦労しました
この違いにより、中央銀行の政策対応も180度異なる方向となりました。
リーマンショック後のFRBは2008年12月から2015年12月まで実質ゼロ金利政策を継続し、量的緩和により市場に資金を供給し続けました。
逆に2022年以降は一転して積極的な利上げ政策に転じ、2022年3月から2023年7月まで11回連続で政策金利を引き上げ、物価高を抑制しようと動きました。
3.今後同様の金融危機が起こる可能性は?
リーマンショックの教訓を受けて金融規制は大幅に強化されましたが、同様の危機が防げるとは限りません。つまり、同様の金融危機が起きないとは言い切れないのです。
また、現代の日本では新たな形のリスクが蓄積されている可能性も指摘されています。
例えば、低金利環境の長期化により蓄積されたリスク投資の拡大です。実際、日銀が2024年3月にマイナス金利政策を解除しました。国内では物価、賃金が上昇傾向にあるため、今後日銀が金利引き上げを行うことで株価が下がって金融危機につながる可能性もあります。
また、暗号資産市場の急拡大や、企業債務の急増も新たなリスク要因として指摘されています。
さらに地政学的リスクも従来以上に金融市場への影響力を増しています。ロシア・ウクライナ戦争や米中対立の激化は、従来のグローバル金融システムの前提を揺るがしており、突発的な市場混乱を引き起こす可能性があります。
最後に気候変動リスクや人口減少といった長期的な構造変化の影響です。確定的なことは予測できないものの、これらの要因が将来的な金融システムの安定性に影響を与える可能性は十分考えられます。
リーマンショックが起きたとき金の価値は上昇している

リーマンショックが起きたとき、世界的不況が起きた中で金の価値は大幅に上昇したことをご存じですか?これは不況になると現物資産の需要が高まり、価値が高騰するためです。金は現物資産であり一度購入すれば手元に残るもので、その後の景気の状況によっては購入時よりも高く売って利益が発生する可能性が高いものです。
金は特に天然の資源であるため、今後希少性が高まることが予想されます。実際に金の市場価値は年々上昇し、早く購入すればするほど後に売却するときには大きな利益が発生する可能性が高いのです。 リーマンショックだけでなく、アメリカ同時多発テロのときにも、世界的な事件が起きた不安から金の買い手が殺到し、価値が大幅に上昇した歴史があります。
今後の不景気の際にも金の価値は上がる?

今後の不景気の際にも、金の価値は上がると予想されます。なぜなら2022年のロシアによるウクライナ侵攻で、金の価格はどんどん上昇しています。 2021年頃が6,000円台だった金の価値が、2023年現在は9,000円後半にまで上昇しています。たった2~3年でここまで金の価値が上がったのは、市場取引がはじまってから最高レベルです。
また、最近は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、経済不安が募ったことも影響し2020年代は金の価値が上がり続けているのです。実際に日本でもコロナ不況と呼ばれ、金の価値が上昇する中でも外食産業やホテルなどの観光産業は大打撃を受けてしまいました。
2023年現在、新型コロナウイルスの警戒レベルが低下したことで、旅行しやすい環境にはなったものの、コロナがない世界だった頃のような状況には戻っていません。 ロシアのウクライナ侵攻も引き続き行われており、今後は中国経済や中東の原油価格なども影響してくると予想されます。
金の資産運用は売却のタイミングが大切

しかし、金は希少価値が高いと言っても必ず価値が大幅に上がるとは断言できません。金に変わるような資源が発見されるなど、何らかの大きな世界的変化によって、今の金の価値が継続する保証はないのです。
それゆえに金は購入してずっと寝かせるのではなく、売りどきを見極めることがとても大切です。 具体的には、一定価格以上になったら売ると決めておいたり、購入から何年以内に手離したりと、自分の中でルールや基準を決めることが大切です。 金は現物資産であり、持っているだけでは利益が生まれません。あくまでも利益が出るタイミングで売却してはじめて価値があるため、取り扱いには注意しましょう。
まとめ

リーマンショックとはリーマンブラザーズの破綻によって広がりを見せた、世界的な経済不況のことです。
2009年に起きた結果、そこから数年にわたり日本の経済にも大きく影響を与えました。 投資家や企業だけでなく、その経営不振になった企業で働いていた派遣の人々も契約が切られてしまい、生活がままならないといった社会問題に発展したのです。そんな中でも金の価値は上昇し、経済不安にともなって買い手の数が増えていく特徴があります。
最近ではロシアのウクライナ侵攻によって、金の価値がますます上昇しています。金の価値は今後も上がるとは予想されますが、いつまでも寝かせているうちに価値が下がる可能性も十分にあります。 だからこそ、価値が上昇している今の段階で売却を検討してみてはいかがでしょうか? 金の売却は一定額以上の利益が出ると、控除対象外になり税金が発生します。それゆえに、数年にわたって売却するなど分割する必要が出てくることもあります。
早めに金貨や金のインゴットをはじめ、貴金属の品物があればお売りください。まねきやではベテランの鑑定士が金の純度を機械とともに判定したうえで、正しい価値での買取をお約束します。 店頭買取だけでなく、出張や宅配買取も承っているため、お気軽にご相談ください。 まねきやの金の買取に関する詳細は次の通りです。

この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。

 0120-213-213
0120-213-213