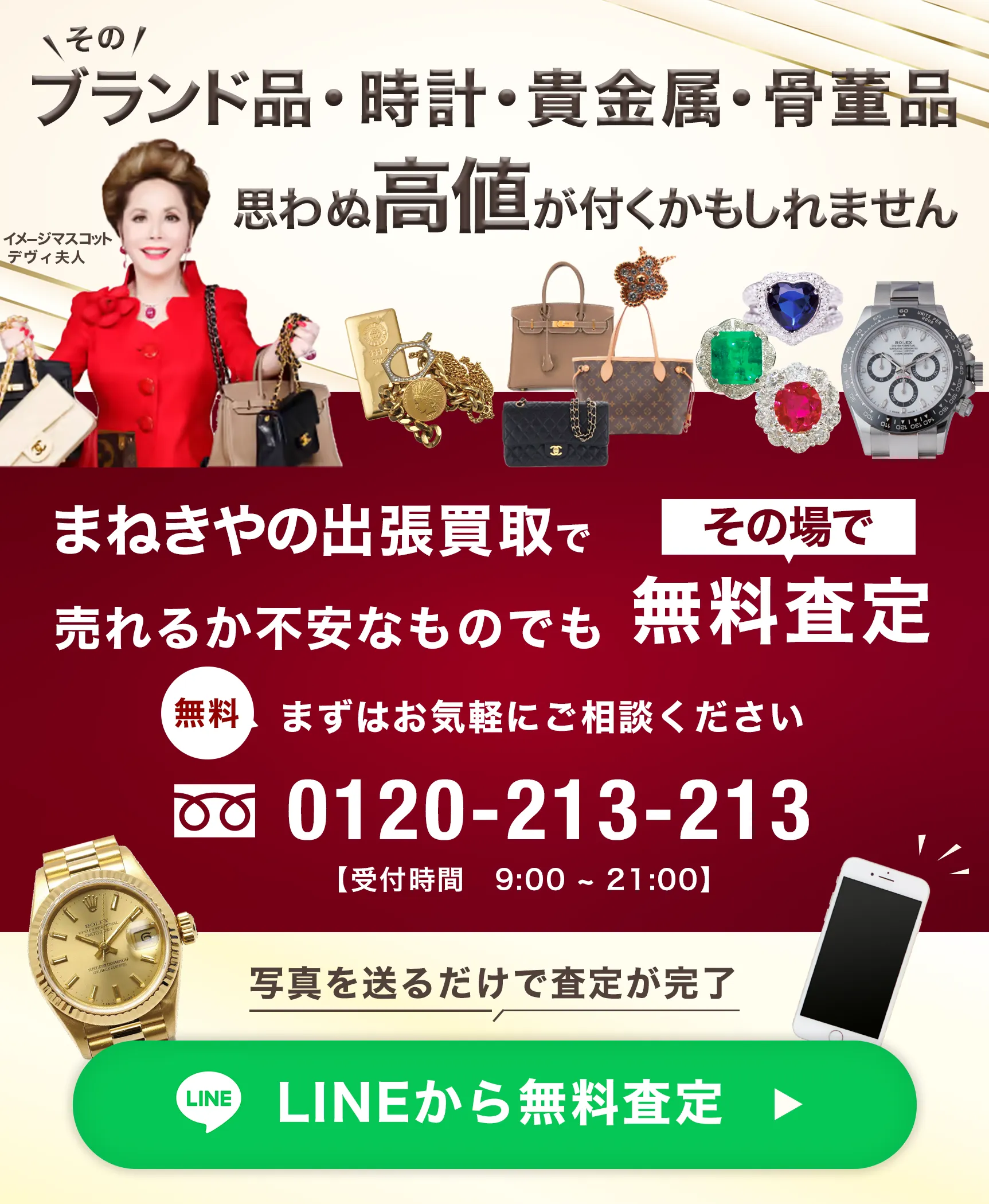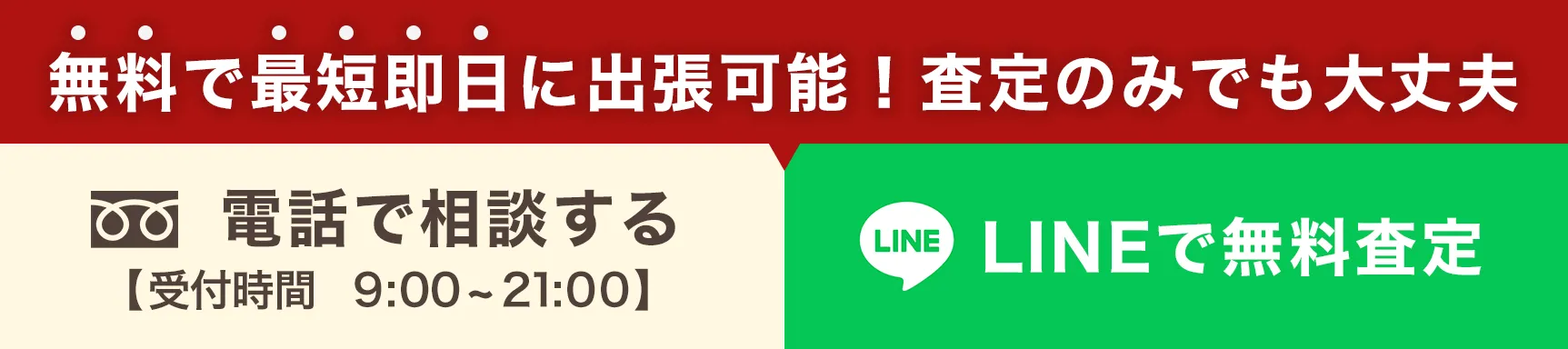和室の気品を際立たせる掛け軸は、古くから日本で愛されてきました。現在も愛好家が多く、希少な品や人気の品は高値で取引されています。
これを読んでいる方のなかにも、「自宅に眠っている掛け軸があるが、どのような種類の掛け軸なのか詳しくわからない」という方がいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、掛け軸の種類や部位ごとの名称、掛け軸をかける際のマナーなどについて解説します。高く売れる掛け軸の特徴も紹介しているので、売却を検討している方もぜひ参考にしてください。
掛け軸とは

日本の伝統的な装飾品である掛け軸は、おもに和室に飾られます。中国から伝わったもので、もともとは仏教の絵画などを描いて拝んでいました。その後、次第に描かれる絵の対象が広がっていき、今日では庶民も気軽に飾って楽しむようになりました。
掛け軸は、絵画や書が描かれた布や紙を木製の軸に巻きつけてあるものが基本の形式です。おもに、茶会の雰囲気を左右する道具の一つとして用いられており、室内空間を美しく演出するのが目的です。また、来客に合わせて床の間(※)の掛け軸を替えるなど、もてなしの意味も込められています。
※ 和室の奥にしつらえた一段高いスペースのこと。畳ではなく木の床が敷かれており、掛け軸や生け花、壺などを飾って趣のある雰囲気を演出する。
掛け軸の種類

掛け軸は、飾る場所に応じて「床の間用」「茶室用」「仏壇用」の3種類に分けられます。ここでは、各種類の掛け軸の特徴を紹介します。
1.床の間用掛け軸
床の間に飾る掛け軸は、日本の伝統的な住空間で用いられる装飾品であり、訪問客をもてなすための重要なものです。「床掛け」とも呼ばれ、床の間の雰囲気づくりにおいて大きな役割を果たします。
床掛けのサイズは、横幅54.5cm、縦190cmのいわゆる「尺五」が一般的です。掛け軸にはいくつかのサイズがありますが、床の間の幅の3分の1のサイズが美しいとされています。
床掛けの題材は自由で、山水画や花鳥画、禅語、俳句などの幅広いテーマが使用されます。来客の趣味や背景に合わせて、趣のある絵や書を選ぶことが望ましいでしょう。
ただし、床掛けは季節感を重視します。春には桜や梅、夏には涼を感じる水辺の風景、秋には紅葉、冬には雪景色など、床掛けの絵柄には四季折々の題材が選ばれます。
とはいえ、絵柄によっては1年中かけておくことも可能です。最小限の色で風景を描く「彩色山水」は、普段掛けに人気ですし、虎や龍など縁起の良い絵柄も季節に関係なく飾ることができます。
そのほか、慶弔にふさわしい掛け軸もあります。代表的なものは、松竹梅や高砂などを描いた「祝儀掛け」、ひな人形や鎧兜などを描いた「節句掛け」です。
2.茶室用掛け軸
茶室では、掛け軸が茶道の精神やその場の趣を伝える重要な役割を担います。茶室の床の間に飾られる掛け軸は「茶掛け」と呼ばれ、茶席で主人が伝えたいメッセージを表現する大切な道具です。
茶掛けでは、禅語や短い詩句のように、シンプルで深い意味を持つ言葉が好まれます。「一期一会」や「和敬清寂」のように季節を問わない言葉もあれば、春の「松樹千年翠」や夏の「山是山水是水」など、季節に合わせて飾る言葉もあります。
また、「墨蹟(ぼくせき)」と呼ばれる僧侶の書いた書を茶掛けとして飾ることも一般的です。長年修行し、立派な書を書いた人を敬う気持ちを込めて飾ります。そのため、自分の書を飾るのはマナー違反です。
なお、茶掛けには季節感を反映しているものも多いため、茶室のしつらえに合わせてその季節のテーマに合った掛け軸を選ぶのもよいでしょう。
3.仏壇用掛け軸
仏壇に飾る掛け軸には、仏像で見かける如来や明王、菩薩など信仰する宗派の仏様が描かれています。僧侶にお経をあげてもらい、仏様の魂が宿った掛け軸は、位牌とともに仏壇へ祀ります。仏壇用の掛け軸の素材は、おもに格式の高い金襴(きんらん)や絹本(けんぽん)が選ばれます。
なお、仏像と掛け軸は同じ役割を担っており、基本的にどちらを選んでも問題はありません。
また、仏壇に飾る場合は、掛け軸をご本尊と両脇仏の3幅対(さんぷくつい)用意する必要があります。ご本尊と両脇仏は各宗派によって異なります。掛け軸の題材や形式も同様に宗派ごとに異なるため、注意が必要です。
例えば、浄土宗の場合はご本尊が阿弥陀如来、両脇仏は左が法然上人で右が善導大師です。日蓮宗の場合はご本尊が御曼荼羅、両脇仏は左が鬼子母神で右が大黒天となります。浄土真宗の場合、ご本尊は阿弥陀如来ですが、両脇仏は各派によって異なります。
掛け軸を購入する場合は、自身がどこの宗派なのかを事前に確認しておきましょう。
掛け軸の形式の種類

書や絵などの作品を掛け軸に仕立てる形式のことを、「表装(ひょうそう)」と呼びます。掛け軸の表装は、大きく「大和表装」と「文人表装」の2種類に分けられます。種類によって掛け軸の格式や意味合いも変わるため、飾る前にそれぞれを理解しておきましょう。
ここでは、それぞれの種類について解説します。
1.大和表装
一般的な掛け軸の形式として多く用いられているのが、大和表装です。以下のように「真」「行」「草」の3つの形式があり、用途に応じて使い分けられます。真は楷書、行は行書、草は草書を意味し、書道に由来しています。
・真
真は、大和表装のなかで最も格式が高い形式です。仏事などの厳かなシチュエーションで使用されることが多く、派手さを抑えた落ち着いたデザインが特徴です。
真は、さらに「真の真」「真の行」「真の草」の3種類に区分されます。掛け軸の部位については後述しますが、最も格上の「真の真」では一文字廻しが施されています。「真の行」は一文字廻しがなく一文字のみ、「真の草」は一文字もありません。
・行
行は、真と草の中間に位置する形式です。ややカジュアルな場面でも使いやすい柔軟性を備えています。仏具以外であれば、山水画や花鳥画などどのような作品にも使用できる表装です。
行も、「行の真」「行の行」「行の草」の3種類に区分されます。格式が下がるにしたがって、一文字廻しや一文字がなくなっていく点も同様です。
・草
「草」は、大和表装のなかで最もカジュアルな形式で、「草の行」と「草の草」の2種類です。行に比べて本紙の横の柱が細く、「草の草」では一文字を省いた形となっています。華美を避ける草の形式は茶道と相性が良く、茶席で茶掛けとして用いられます。
2.文人表装
中国王朝の時代に広まった文人表装は、日本でも江戸時代に流行しました。
落ち着いた色調と簡素なデザインが特徴の表装形式で、書画や水墨画など、書と絵のどちらにも使用されます。華美な装飾を排し、主題となる作品を引き立てる役割を果たします。文人表装は、特に茶道や日本文化を重んじる場に適しています。
文人表装は、大和表装と異なり中廻しと外廻しを区別しません。一種類の裂地で本紙を囲っており、見る人に簡素な印象を与えます。「風帯」と呼ばれる、掛け軸の上から下がる2本の細い帯がないのも文人表装の特徴です。
また、文人表装には、丸表装や明朝表装などの種類があります。丸表装は1種類、もしくは2種類の裂地を使ったシンプルな仕立てで、袋表装とも呼ばれます。明朝表装は、この丸表装の両側に「明朝」と呼ばれる縁をしつらえたものです。
日本では、漢詩や漢文、南画などを仕立てる際に文人表装を用いることが多いようです。
掛け軸の部位ごとの名称

掛け軸の絵や書は、「表装」と呼ばれる技術で仕立てられますが、布地や紙の細かな部分にも名称があります。それぞれの部位がバランス良く調和して、掛け軸の美しさを引き立てているのです。
掛け軸は、絵や書が描かれた作品部分の「本紙」とそのほかの部分を総称した「表紙」で大きく区別されます。表紙の構成要素は非常に多いため、以下でその一部を解説します。
表紙のおもな構成要素
|
八双(はっそう) |
掛け軸の最上部にある半円形の棒 |
|
風帯(ふうたい) |
八双から本紙にかけて下がる細い2本の帯。 |
|
天地(てんち) |
中廻しの上下の部分で、上を「天」、下を「地」と呼ぶ |
|
中廻し(ちゅうまわし) |
本紙の上下の部分 |
|
一文字(いちもんじ) |
本紙の上下にある横長の裂(きれ) |
|
柱(はしら) |
本紙の左右の部分 |
|
軸木(じくぎ) |
掛け軸の最下部にある棒で「軸棒」とも呼ぶ。 |
このほかにも、掛け軸を吊るすための「掛紐」や、本紙を囲う細い裂地である「筋」などがあります。表装の各部位に使われている裂地の種類や軸先の材質なども、掛け軸を鑑賞する際の見どころです。
掛け軸をかける際のマナー

掛け軸で風情漂う空間を演出するためにも、ここでは掛け軸をかける際のマナーを紹介します。
まず、掛け軸をかける場所は床の間でなくても問題はありません。洋室に合う表装を採用した掛け軸も存在するため、部屋の雰囲気に合った掛け軸選びを心がけましょう。
掛け軸をかける際は、矢筈(やはず)と呼ばれる棒を使います。高い位置でも矢筈があれば踏み台なしで飾ることができ、ずれてしまった場合もすぐに調整ができます。
また、掛け軸に影がかからないようにすることも重要です。床の間に壺や生け花などを飾る際、光源の位置によって掛け軸に影が映り込むと見栄えが悪くなるためです。
掛け軸をかける高さも重要です。本紙の真ん中が鑑賞者の視線よりすこし高い位置にくるのが正しいとされています。
大切な掛け軸を長く楽しむためには、保管方法や扱い方にも注意を払いましょう。
掛け軸は紙でできています。カビが生えないよう、収納する際は薄い和紙で包み、桐箱に入れて乾燥した場所で保管してください。また、季節に合わせて数ヵ月ごとに掛け軸を交換すると長持ちしやすいでしょう。長期間かけっぱなしにすると、冷暖房の風や直射日光で劣化してしまうため注意が必要です。
高く売れる掛け軸の特徴

ここからは、高く売れる掛け軸の特徴を3つ紹介します。
1.有名作家の作品
掛け軸は、著名な画家や書家が手がけたものほど高い評価を受けます。著名な作家の例としては、円山応挙(まるやまおうきょ)や富岡鉄斎(とみおかてっさい)などが挙げられます。ただし、有名な作家ほど贋作も多いので注意が必要です。
掛け軸の価値は、作家の経歴や技術力、知名度にも大きく左右されます。売却を検討しているときは、掛け軸の落款(らっかん)や署名から有名作家のものかを確かめてみるとよいでしょう。
2.保存状態が良好
掛け軸の保存状態も価値に大きく影響します。掛け軸は湿気や日光などの影響を受けやすく、繊細な扱いが求められる美術品です。保存状態が良好で、シミや破れのないもの、色褪せのないものほど高価買取が期待できます。日頃から丁寧に扱うことが大切です。
なお、状態の悪い掛け軸を自分で補修しようとすると、かえって汚したり傷つけたりしてしまう場合があります。売却の際は、そのままの状態でプロに鑑定してもらいましょう。
箱や鑑定書などの付属品がある場合は、併せて提出することで査定額アップにつながります。
3.歴史的・文化的価値のあるもの
江戸時代や明治時代に制作されたもの、また特定の文化的な背景を持つ作品は特に需要が高い傾向です。
基本的に、年代が古い掛け軸ほど現存している数が少なく、その分希少価値も高くなります。作者が不明でも、制作年代が古く、保存状態が良好なら高値が付く場合もあるでしょう。
掛け軸を売るならまねきやがおすすめ

和室に趣を与える掛け軸は、古くから日本で愛されてきた美術品です。掛け軸には、季節感のある絵柄で部屋の印象を変えたり、格式の高い表装で来客をもてなしたりする役割もあります。
ただし、掛け軸を飾る際は、影が映らないようにすることや適切な高さにかけるなど、知っておきたいことがいくつかあります。また、長く楽しむためにも適切な方法で保管しましょう。
お手持ちの掛け軸を売却する際は、専門知識を持つ業者に査定を依頼することが重要です。「まねきや」では、経験豊富なスタッフが掛け軸を査定し、適正価格で買い取りいたします。
大切な掛け軸を納得のいく価格で売りたい方は、ぜひまねきやの無料査定をご利用ください。

この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。

 0120-213-213
0120-213-213