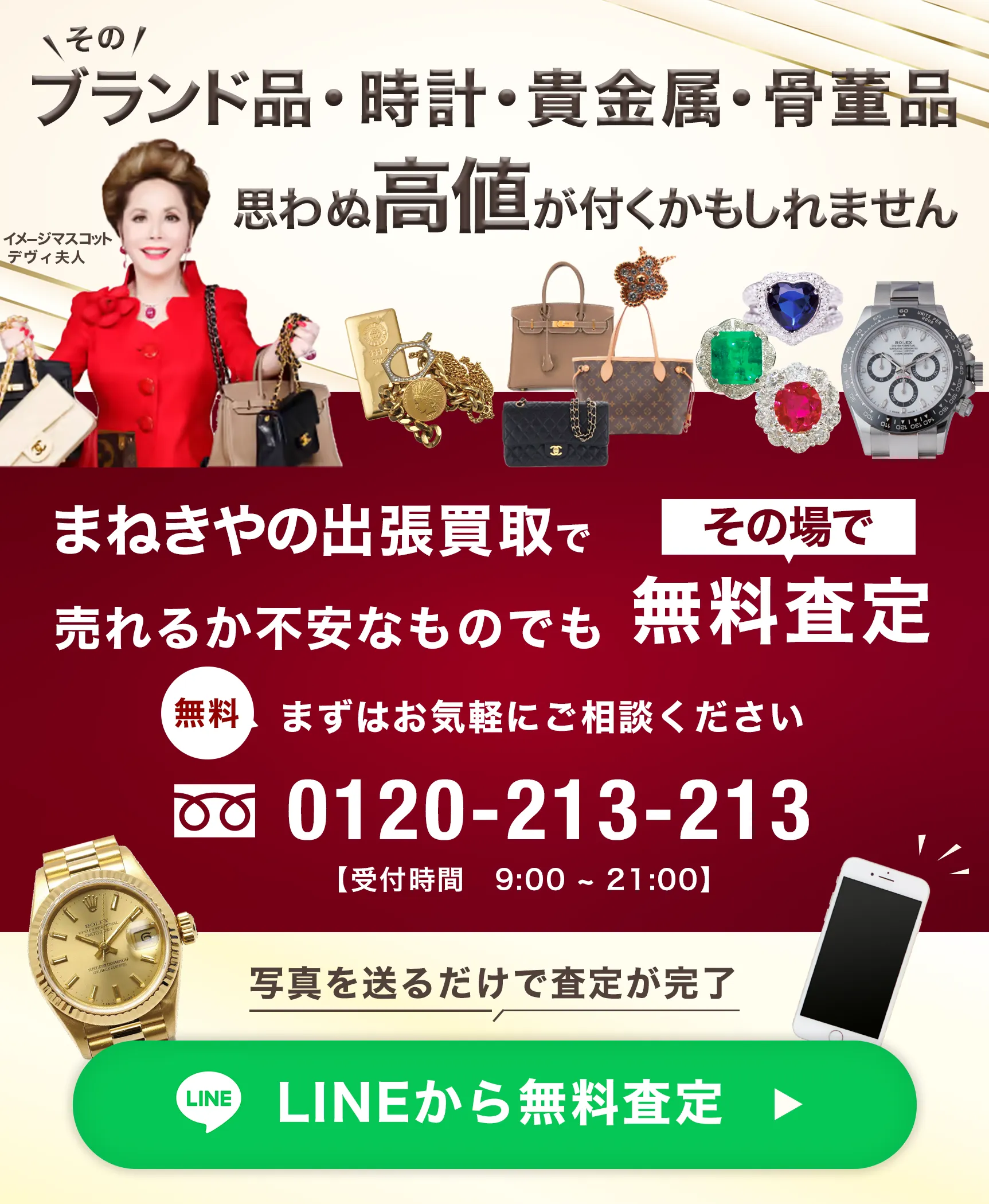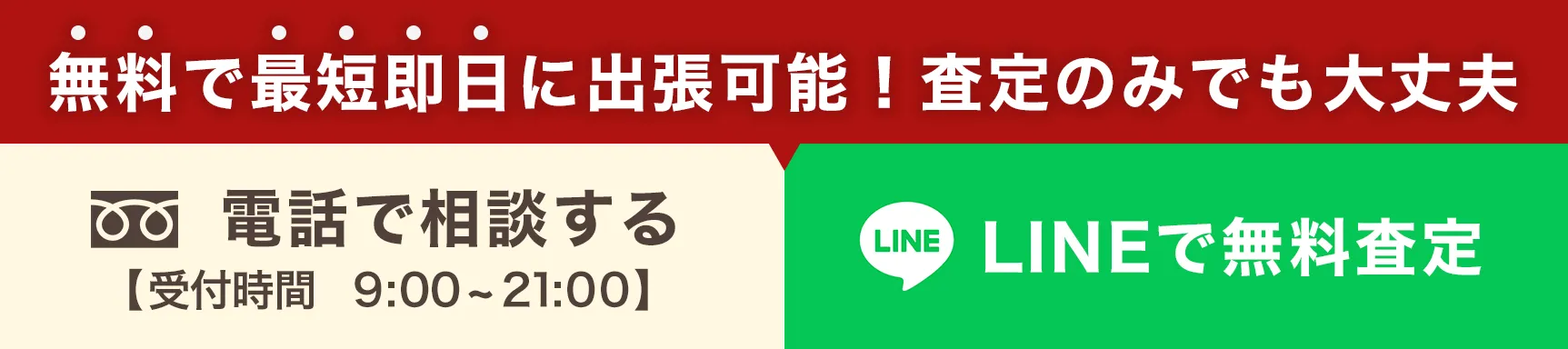自分が持っている古いお札にどれくらいの価値があるのか、気になっている方もいるでしょう。古いお札には、歴史的価値や希少価値によって、額面以上の価値が付くことがあります。実際、自宅で今は製造されていない紙幣を見つけ、どうすればいいかわからず買取査定を依頼する方も多いです。
この記事では、古いお札の価値や高く売れるお札の特徴、代表的なお札の相場を紹介いたします。手もとの古いお札の売却を検討している方は、ぜひご参考にしてください。
「古いお札って、見つけたらどうすればいいの?」
「そもそもこのお札って本物?」
このように悩んでいる方は、ぜひ記事を読んで手元のお金が何かを特定し、その価値を探ってみてください。
旧紙幣・古紙幣とは?

一般的に、旧紙幣・古紙幣とは年代が古く、現在ではもう使われていない通貨を指します。日本で、お札=紙幣が使われるようになったのは明治時代のことです。明治以降に発行されたもので、今は使われていない紙幣を旧紙幣・古紙幣と呼んでいます。
また、旧紙幣や古紙幣にはさまざまな形状やデザインがあり、それぞれのお札には発行当時の時代背景や歴史的な出来事、文化などが反映されています。 旧紙幣と古紙幣の違いは、通貨として使用できるかどうかです。
旧紙幣は普段は使われていませんが、現金として使用できます。例えば、聖徳太子の1万円札であれば、1万円のショッピングに利用可能です。一方、古紙幣は額面に関わらず、通貨としての利用はできません。
このように、明治時代に作られた古い紙幣であっても、通貨として使用可能であれば、古紙幣ではなく旧紙幣と呼ばれます。
なお、通貨として利用できるかどうかは、日本銀行や財務省のホームページなどで確認できます。例えば、2024年2月現在、大黒天が描かれた明治18年発行の旧1円券(※)は、財務省のホームページに掲載されている情報によれば、通貨として使用可能です。
※参考:財務省「昔のお金は使えますか」 https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ad.htm
ただし、旧紙幣は、コレクション品としての価値が高い可能性があります。そのため、普通にお金として使ってしまうと、実際の価値よりも損をするかもしれない点に注意しましょう。
また、歴史的な価値や美術的な価値がある古い紙幣は、多くのコレクターの注目を集めています。
旧紙幣・古紙幣の種類と価値

ここからはそれぞれの旧紙幣がどのような特徴、価値をもつのか具体的に見ていきましょう。ここで紹介するのは、以下17種類の古紙幣です。
- 10,000円紙幣(旧10,000円札)
- 5,000円紙幣(旧5,000円札)
- 2,000円紙幣
- 1,000円紙幣(旧1,000円札)
- 500円紙幣(500円札)
- 200円紙幣(200円札)
- 100円紙幣(100円札)
- 50円紙幣(50円札)
- 20円紙幣(20円札)
- 10円紙幣(10円札)
- 5円紙幣(5円札)
- 2円紙幣(2円札)
- 1円紙幣(1円札)
- 50銭紙幣(50銭札)
- 20銭紙幣(20銭札)
- 10銭紙幣(10銭札)
- 5銭紙幣(5銭札)
ご自宅にある紙幣を手元に用意して、見比べながらチェックしてみてください。以下を読めば、お手元の古紙幣のおおまかな価値がわかります。
1.10,000円紙幣(旧10,000円札)
価値のある旧10,000円札の代表格として、昭和33年(1958年)から発行された聖徳太子の10,000円札がよく知られています。日本初の10,000円紙幣として歴史的価値が高く、その威厳ある肖像画は多くの人の記憶に残っています。
券面には聖徳太子の肖像が、裏面には2羽の鳳凰が描かれているのが特徴的です。また、昭和59年からは福澤諭吉の10,000円札も発行されており、こちらは表面に福澤諭吉、裏面に雉が描かれた精緻なデザインとなっています。(発行年により2つの異なるデザインがある)
買取額の例
- 聖徳太子が描かれた10,000円札:10,000〜100,000円前後
- 福沢諭吉が描かれた10,000円札(裏面に雉が2匹のもの):10,000〜17,000円前後
比較的取引量も多いため、それほど高額での取引にはならないのが一般的です。ただ、プリントエラーや紙幣に記載された番号の並び順によっては買取額が額面が10倍以上になる場合もあります。
なお、福沢諭吉が描かれた10,000円札(裏面が平等院鳳凰堂鳳凰像のもの)は、裏面に雉が2匹のものよりも買取額が低くなります。
2.5,000円紙幣(旧5,000円札)
旧5,000円札では、昭和32年(1957年)から発行された聖徳太子の5,000円札が最も古い紙幣として知られています。10,000円札と同じく聖徳太子が描かれていますが、こちらの方が古くから発行されているのが特徴です。
券面デザインは聖徳太子の肖像を中央に据え、裏面には東京都中央区にある日本銀行本店本館が描かれています。その後は表面に新渡戸稲造、裏面には逆さ富士が描かれた紙幣、表面に樋口一葉、裏面に尾形光琳の「燕子花図(かきつばたず)」が描かれた紙幣へと変遷していきます。
旧5,000円札は、どのデザインも額面とほぼ同額での買取となります。エラーがあったり紙幣に記載された番号の並び順が珍しかったりすると買取額が高まる場合もあるため、気になる方は専門知識を持つ鑑定士が在籍する買取業者に相談してみましょう。
3.2,000円紙幣
2,000円札は平成12年の沖縄サミット開催を記念して発行された特別な紙幣です。額面の珍しい設定と、他の紙幣と比べて発行枚数が少ないことが特徴です。
表面には沖縄の首里城の守礼門が描かれ、裏面には源氏物語絵巻の一場面と紫式部の肖像が配されています。鮮やかな紫色を基調としたデザインは他の紙幣とは異なる存在感があります。
2,000円紙幣は現在でも法定通貨として使用できるため、額面通りの2千円が基本です。ただし流通量が少なく現在同額面の紙幣は発行されていないため、今後価値が高まる可能性もあります。
4.1,000円紙幣(旧1,000円札)
1,000円紙幣には以下5つのデザインが存在します。
- 表面:日本武尊/裏面:「千圓」の文字(昭和20年発行)
- 表面:聖徳太子/裏面:法隆寺夢殿(昭和25年発行)
- 表面:伊藤博文/裏面:日本銀行本店本館(昭和38年発行)
- 表面:夏目漱石/裏面:丹頂(昭和59年発行)
- 表面:野口英世/裏面:富士山と桜(平成16年発行)
旧11,000円札の中でも特に価値が高いのが、日本武尊が描かれた11,000円札です。日本初の1千円紙幣として歴史的意義が深く、10〜25万円前後で取引されます。
その他の紙幣の買取額の目安は以下の通りです。
- 聖徳太子が描かれた1,000円紙幣:〜15,000円
- 伊藤博文が描かれた1,000円紙幣:額面〜8,000円前後
- 夏目漱石が描かれた1,000円紙幣:額面通り
- 野口英世が描かれた1,000円紙幣:額面通り
日本武尊が描かれた11,000円札以外でも額面を超える買取額になる場合があります。特に昔に発行されたデザインの紙幣ほどその可能性が高くなるため、気になる方は一度買取業者に査定を依頼してみましょう。
5.500円紙幣(500円札)
500円札は昭和26年から発行された岩倉具視の肖像が描かれた日本最後の500円紙幣で、硬貨への移行により平成6年に発行停止となった、歴史的な節目を象徴する紙幣です。紙幣から硬貨への移行期を物語る貴重な存在として、独特の価値を持っています。
表面には明治維新の立役者「岩倉具視」の肖像が描かれ、裏面には富士山が雄大に描かれているのが特徴です。
実は500円紙幣には2種類のデザインがあります。どちらも岩倉具視と富士山が描かれていますが、新しいデザインの券面には盛り込まれた新たな印刷技術や偽造防止技術が踏襲されています。
買取額の例
- 旧デザイン:額面〜5,000円前後
- 新デザイン:額面通り
「500」の文字が表面の四隅に配置されている旧デザインの500円札は、高めの売却額になりやすいです。
6.200円紙幣(200円札)
200円紙幣は、昭和2年から昭和21年まで発行されていた、歴史的な価値を持ち合わせている通貨です。大正時代から何度も発行の構想がなされたが実現せず、昭和2年についに発行されたものの運用がうまくいかなかった特殊な紙幣の一つです。
発行年ごとにデザインが異なり、その価値もさまざまです。
200円紙幣のデザインと価値
- 裏面が真っ白の200円紙幣:50〜300万円前後
- 裏面に赤字の彩文が施された200円紙幣:10,000〜200,000円前後
- 表面に藤原鎌足の肖像、裏面には日本武尊が配された200円紙幣:1,000〜50,000円前後
それぞれ、未使用品なら額面の100倍以上の価値を持つ貴重な紙幣です。コレクター需要も高いため、手元にある場合はすぐに一度査定依頼に出してその価値をチェックしましょう。
7.100円紙幣(100円札)
100円札の代表格として、昭和28年から発行された板垣退助の100円札が特に知名度が高く、「板垣死すとも自由は死せず」の名言で知られる自由民権運動の指導者の肖像が印象的な紙幣です。戦後復興期を象徴する紙幣として、多くの日本人にとって馴染み深い存在となっています。
表面には板垣退助の威厳ある肖像画が中央に配置され、裏面には国会議事堂が描かれています。その前には聖徳太子の100円札も発行されており、こちらは「法隆寺西院伽藍」や「法隆寺伽藍」が裏面に描かれた格調高いデザインが特徴です。
買取額の例
- 聖徳太子が描かれた100円札:200〜8,000円前後
- 板垣退助が描かれた100円札:額面〜5,000円前後
他にも明治時代のものを含めると、大黒天が描かれたものや聖徳太子が描かれたデザインなどさまざま存在します。それらは真贋や価値の鑑定が難しいため、一度専門知識を持つ鑑定士が在籍する買取業者に鑑定してもらいましょう。
8.50円紙幣(50円札)
50円札は昭和26年から昭和33年のわずか7年間のみ発行された紙幣です。高橋是清の肖像が描かれた紙幣で、「日本のケインズ」と呼ばれた偉大な財政家の功績を称える歴史的意義の深い紙幣として価値を持っています。
表面には温和な表情の高橋是清の肖像が配され、裏面には東京都中央区にある日本銀行本店の建物が精密に描かれています。
買取額は保存状態によって価値が大きく変動するのが一般的です。
- 並品:200円~500円前後
- 美品:500円~1,500円前後
- 未使用品:1,500〜4,000円前後
なお、未発行とされる超貴重品「甲号券50円札」という紙幣も存在します。もし裏面が真っ白の50円札を見つけた場合、かなり貴重な品である可能性があるため、厳重に保管して専門知識のある鑑定士のいる買取業者に査定を依頼しましょう。
9.20円紙幣(20円札)
20円札は昭和5年から昭和21年にかけて発行された珍しい額面の紙幣です。個人が買取に持ち込むケースも稀ながらあり、額面を遥かに上回る買取額がつくことがあります。
表面には藤原鎌足の肖像が描かれ、裏面には談山神社拝殿が配されているのが特徴です。表面の額面表記が縦書きであることから、「タテ書き20円札」とも呼ばれます。
藤原鎌足が描かれた20円紙幣希少であるため、未使用品なら10,000円を超える価値がつくこともあります。使用感があっても美品であれば5,000円前後で取引されるため、手元にある方は状態が悪化しないように冷暗所で保管しておきましょう。。
上記以外の特徴を持つ20円札はさらに古い紙幣であることが予想されるため、見つけたら一度、専門知識のある鑑定士のいる買取業者に真贋を判定してもらうのがおすすめです。
10.10円紙幣(10円札)
10円札にも数多くのデザインが存在しますが、代表的なのは和気清麻呂が肖像に描かれた紙幣です。奈良時代の官人であった和気清麻呂が、天皇の位を狙う僧侶弓削道鏡の野望を阻止し暗殺されそうになったとき、突如現れたイノシシの大群に命を救われたエピソードにちなんで、紙幣にもイノシシがデザインされています。
和気清麻呂が表面にデザインされた紙幣にもさまざまな種類があり、価値もまちまちです。
10円紙幣の特徴と価値
|
紙幣名 |
見分け方(デザインの特徴) |
買取価格例 |
|
表猪10円札 |
表面の和気清麿、縁取りされた猪の図柄 |
10〜80万円前後 |
|
裏猪10円札 |
裏面中心のイノシシの図柄 |
1〜50万円前後 |
|
左和気10円札 |
表面左側に印刷された和気清麿の肖像 |
1,000〜20,000円前後 |
|
和気清麻呂(4種類) |
表面は4種類とも和気清麿、縦書きで捨圓の文字が描かれる。裏のデザインは種類によってさまざま |
額面〜20,000円前後 |
10円札は旧紙幣全体の中でも発行種類が豊富で、上記以外にもさまざまな絵柄のものがあります。なかには買取額が100万円を超える紙幣もあるため、見つけたら状態が悪化しないように保管しておきましょう。
11.5円紙幣(5円札)
5円札は、学問の神様として親しまれる平安時代の廷臣の威厳ある姿が印象的な「菅原道真」の肖像が描かれた紙幣が代表的です。特に有名な「分銅5円札」と呼ばれる紙幣は、表面中央に分銅のようなデザインが配されたことからその名で呼ばれています。
代表的な5円紙幣の特徴とその価値
|
紙幣名 |
見分け方(デザインの特徴) |
買取価格例 |
|
分銅5円札 |
表面中央の分銅のようなデザインと、菅原道真の肖像 |
5〜35万円前後 |
|
中央武内5円札 |
表面中央の武内宿禰の肖像と、裏面の赤字で書かれた「NIPPON GINKO」の文字 |
5,000〜100,000円前後 |
|
菅原道真 1〜4次 |
菅原道真が右側に、北野天満宮が左側に描かれた券面 |
50〜8,000円前後 |
菅原道真が描かれた紙幣が多く、その他にも武内宿禰や大黒天が描かれた紙幣などさまざまなデザインが存在します。似たデザインでも発行時期によって価値が異なる場合があるため、素人での判断が難しいのも5円紙幣の特徴の一つです。
12.2円紙幣(2円札)
2円札は明治初期に発行された極めて珍しい額面の紙幣で、明治5年の明治通宝2円札と明治6年の旧国立銀行券2円札の2種類のみが存在する、古紙幣の中でも類を見ない希少性を誇っています。
2円紙幣の特徴とその価値
|
紙幣名 |
見分け方(デザインの特徴) |
買取価格例 |
|
明治通宝2円札 |
縦書きのデザインで、金二圓の文字が描かれている |
4,000〜50,000円前後 |
|
旧国立銀行券2円札 |
新田義貞と児島高徳が表面の両側に描かれている |
10万円以上 |
旧紙幣全体の中でも2円札は発行期間の短さと現存数の少なさにより、最高レベルの希少価値を持っています。特に旧国立銀行券2円札はコレクターにも人気があり、未使用品でなくても10万円以上になる場合が多いです。
13.1円紙幣(1円札)
1円札では表面右側に大黒天が描かれた「大黒1円札」が現存数の少ない貴重な紙幣として高い価値を誇ります。使用品で5,000〜30,000円、未使用品であれば8〜20万円になる可能性もあるほどです。
他にも、さまざまなデザインの1円札が存在します。
1円紙幣の特徴とその価値
|
紙幣名 |
見分け方(デザインの特徴) |
買取価格例 |
|
旧国立銀行券1円 |
表面に武将と軍船、裏面に描かれた蒙古襲来の様子 |
3〜25万円前後 |
|
漢数字1円札 |
表面右側の武内宿禰の肖像と、中央の壱圓の文字 |
1,500〜20,000円前後 |
|
二宮尊徳1円札 |
表面右側に描かれた二宮尊徳の肖像 |
10〜50円 |
デザインによってその価値はさまざまです。上記以外にも縦書きの明治通宝や、漢数字1円札の漢数字の部分がアラビア数字になっているものなど、バリエーションがさまざまあります。
査定する鑑定士によって査定額が異なる場合もあるため、複数の業者に査定してもらい、高値をつけた業者に買い取ってもらうのがおすすめです。
14.50銭紙幣(50銭札)
50銭札は明治時代から昭和時代にかけて発行された小額紙幣で、中でも板垣退助の肖像が描かれた昭和期の50銭札が最も新しいです。自由民権運動の指導者として知られる板垣退助の温和な表情は、戦後復興期の希望を象徴するデザインとして多くの国民に愛用されました。
表面には板垣退助の肖像画が配され、シンプルながらも品格のあるデザインが特徴です。その他にも、戦時中には富士山と桜を描いた「富士山50銭札」や靖国神社を配した「靖国50銭札」も発行されており、それぞれ時代背景を色濃く反映したデザインとなっています。最も古い大蔵卿50銭札は菊花紋章が印象的な格調高い仕上がりです。
買取額の例
- 大蔵卿50銭札:5,000〜100,000円前後
- 富士山50銭札:10〜300円前後
- 靖国50銭札:20〜400円前後
- 板垣50銭札:100円前後
大蔵卿50銭札以外は買取価格が低めに止まっていますが、特定の印刷所で発行されたものやエラーがあるものは高い価格がつくこともあります。
詳しい価値を知りたい場合は、専門知識のある鑑定士に査定を依頼してみましょう。
15.20銭紙幣(20銭札)
20銭札は明治時代から大正・昭和時代にかけて発行された小額紙幣です。特に大蔵卿20銭札は使いやすい金額設定から発行枚数が多く、庶民の日常生活に密着した身近な紙幣として親しまれていました。発行枚数が多かった一方、いまだに高額で取引されている珍しい紙幣です。
大蔵卿20銭札より前に発行された最初期の明治通宝20銭札は、政府による統一貨幣制度の象徴として、ドイツの印刷技術を用いた精密な作りが特徴です。
一方、前述の大蔵卿20銭札は菊花紋章を中心とした伝統的なデザイン、最も新しい大正小額政府紙幣20銭札は大正時代の新しい印刷技術による緑色が特徴で、洗練された仕上がりとなっています。
買取額の例
- 明治通宝20銭札:500〜8,000円前後
- 大蔵卿20銭札:1,000〜15,000円前後
- 大正小額政府紙幣20銭札:300〜5,000円前後
旧紙幣全体の中で20銭札は小額紙幣でありながら、比較的高値で取引されることが多いです。
16.10銭紙幣(10銭札)
10銭札は明治・大正・昭和時代に発行された紙幣です。明治・大正時代の1円が今の4,000円前後の価値を持っていた時代において、庶民の日常的な小額取引に欠かせない実用的な紙幣として重要な役割を果たしていました。戦時中から戦後復興期にかけては金属不足のため10銭硬貨の代替として紙幣が発行され続けました。
明治時代を代表する10銭紙幣は縦書きの明治通宝10銭札で、政府による統一貨幣制度の一環として発行されました。
大正小額政府紙幣10銭札は大正時代の印刷技術を反映した精密な仕上がりで赤い券面が特徴です。昭和期には八紘一宇塔が描かれた「い号券10銭札」や鳩をモチーフにした「A号券10銭札」も発行され、それぞれ時代背景を色濃く反映した特徴的なデザインとなっています。
買取額の例
- 明治通宝10銭札:1,000〜10,000円前後
- 大正小額政府紙幣10銭札:10〜5,000円前後
- 八紘一宇塔10銭札:10〜100円前後
明治・大正時代の10銭紙幣は状態によっては1,000円を超える買取価格がつくものの、昭和時代の10銭紙幣はやや買取額が低めになる傾向があります。
17.5銭紙幣(5銭札)
5銭札は戦時中の金属不足により硬貨の代替として発行された特殊な経緯を持つ紙幣です。デザインは全部で2種類あり、楠木正成の勇壮な騎馬像が描かれた「楠公像5銭札」が印象的な存在として知られています。
鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した忠臣の武勇を称えるデザインです。楠公像5銭札は昭和19年から発行され、表面に楠木正成の騎馬像が力強く描かれています。
戦後に発行された「梅5銭札」は一転して平和的なデザインとなり、左側に漢字で「五銭」、右側に美しい梅の花が大きく配されたシンプルで上品な仕上がりです。サイズも小さくなり、戦後復興期の新しい時代への転換を象徴しています。
どちらも買取額は100円未満ですが、今後価格が高まる可能性もあるため、一度査定した上で、持っておくか売却するかを決めるのがおすすめです。
価値が高い旧紙幣・古紙幣の特徴

価値が高い旧紙幣・古紙幣にはいくつかの特徴があります。ここでは代表的な特徴を紹介しましょう。
1.希少性が高い紙幣
発行された枚数や現存する枚数が極めて少ないケースや、特定の条件の下で限定的に発行されたケースでは、その紙幣の価値が高くなることがあります。希少価値の高い紙幣は市場にめったに出回らず、需要が供給を上回るのが一般的です。
また、100枚の束になった帯付きの紙幣なども、旧紙幣・古紙幣では非常に珍しく、希少性が高いとされています。
2.歴史的な出来事や人物を記念した紙幣
歴史上の出来事を記念した紙幣や、特定の人物を称えた紙幣などは、その時代の雰囲気を感じさせるお札として人気があります。そのため、高い価値が付きやすいことが特徴です。
3.美術的な価値が高いデザインの紙幣
有名なアーティストがデザインした紙幣や、デザイン自体が優れている紙幣は、美術的な価値が高いことがあります。デザイン性に優れた紙幣は、古銭・古札コレクターだけでなくアートコレクターにとっても魅力的で、価値が高いといえるでしょう。
4.エラーや誤刷が含まれている
エラーや誤刷(印刷ミス)がある紙幣は、コレクターの間で人気があります。通常、エラーや誤刷があっても、市場に出回る前に取り除かれます。そのため、極めて珍しいお札といえるでしょう。
エラーや誤刷には、紙が折れた状態で印刷されたため、端のカットが不完全で余分な紙が残っている「耳付き」のものや、インク汚れや印字にズレがあるもの、表裏で番号が異なっているものなどがあります。
5.保存状態のよい紙幣
古いお札は経年劣化が進んでいると考えられますが、保存状態によっては傷みが少なく、きれいな状態で残っていることがあります。そのような場合、お札の価値が高くなります。未使用で保存状態が良ければ、さらに高くなるでしょう。
価値の高い旧紙幣・古紙幣(日本編)

ここでは、価値が高い日本の旧紙幣・古紙幣を4つ紹介します。
1.旧国立銀行券
旧国立銀行券は、古紙幣のなかでも最も価値が高いといわれています。1873年から「兌換紙幣」として発行されています。兌換紙幣とは、金との交換ができる紙幣のことです。
この紙幣は、日本が金本位制を採用した際の象徴ともいえるでしょう。発行された枚数が少なく、1899年には使用が禁止されました。回収が進んだため、現存する枚数も少ないといわれており、保存状態によってはかなりの価値があります。
例えば、5円札の未使用品の価値は150万円程度であり、さらに20円札の未使用品は2,000万円程度の価値があります。
2.大黒札
大黒札とは、1885年から発行された日本銀行の最初の紙幣です。券面には大黒天が描かれており、通称「大黒札」と呼ばれています。正式には「日本銀行兌換銀券」といい、「兌換銀行券」などとも呼ばれます。
この紙幣は、金ではなく銀との交換ができるもので、券面の色味は偽造防止のために青インクで印刷されているのが特徴です。
大黒札の種類は、1円札、5円札、10円札、100円札の4種類です。1円札は前述したように通貨として使用できるので、「旧紙幣」と呼ばれ、ほかは「古紙幣」と呼ばれます。状態によって異なりますが、一般的に100円札は数百万円の価値になることがあります。5円札と10円札の場合は数十万~百万円程度、1円札は数万~数十万円程度です。
3.分銅 5円紙幣
分銅 5円紙幣は、1888年から発行された日本銀行の兌換銀券で、券面には菅原道真が描かれています。表面中央には分銅のようなデザインがあるため、「分銅 5円」と呼ばれています。この紙幣は希少性が非常に高く、状態のよいものだと150万円近くになる可能性もあるでしょう。
4.大和武尊 千円紙幣
大和武尊千円は、1942年から1946年の戦時中から終戦直後にかけて発行された昭和時代の古紙幣です。正式には「兌換券甲号1000円」と呼ばれています。券面には大和武尊の人物が描かれ、建部大社の絵柄も特徴です。戦時中の状況で高額な紙幣として発行されたものの、短期間で使用が終わり、回収が進んだので希少性が高くなっています。そのため、数万円~数十万円になることもあります。
価値の高い旧紙幣・古紙幣(海外編)

ここでは、価値の高い海外の旧紙幣・古紙幣を紹介します。
1.ソビエト連邦の紙幣
かつてのソビエト連邦(ソビエト社会主義共和国連邦)は、アメリカとの間で東西冷戦を繰り広げた社会主義陣営の超大国でしたが、1991年に崩壊しました。1922年の設立から約70年間発行されたソビエト連邦の紙幣は、今ではもう発行されていませんが、高い人気を誇っています。
ルーブル紙幣は、1ルーブル、5ルーブル、10ルーブル、50ルーブル、100ルーブル、500ルーブル、1000ルーブルなどの額面の紙幣がありました。
2.ペンゲー紙幣
ペンゲー紙幣は、1927年から1946年にかけてハンガリーで使われていた紙幣です。第二次世界大戦の終わりには、ハイパーインフレーションが起こり、非常に高額な紙幣も発行されました。
実際には、1億兆に相当する1垓ペンゲーまで発行されています。さらに計画では、その10倍の10億兆に相当する10垓ペンゲーまで用意されていました。
しかし、ペンゲーの価値が急激に暴落したため、実際にはそのような高額な紙幣でもあまり価値がありませんでした。これらのペンゲー紙幣は、通貨としての価値よりも古いお札としての価値が高いとされています。
3.ディナール紙幣
イラクの通貨であるディナール紙幣は、1931年から発行されています。特にサダム・フセイン元大統領の顔が描かれた紙幣はコレクターの間で人気があり、高額で取引されることがよくあります。
旧紙幣・古紙幣を売る方法は?

ここでは、古いお札を売る方法を紹介します。売却場所はいくつかありますが、それぞれの特徴を知ることが大切です。
1.専門の買取業者
旧紙幣・古紙幣を売る方法として、一般的におすすめできるのが専門の買取業者を利用した売却方法です。買取業者は紙幣の額面価値ではなく、プレミアムを考慮して買取価格を査定します。そのため、旧紙幣・古紙幣の価値を正確に判断し、価値に見合った高値を提示してくれる可能性が高いでしょう。
取引方法には、おもに以下の3つがあります。
- 店頭買取:自分の都合のよい良いタイミングで買取店に持ち込み、査定から代金の受け取りまでおこ行なう
- 出張買取:自宅まで査定スタッフが訪問し、その場で査定を受け、代金を受け取る
- 宅配買取:宅配キットなどで送付し、査定を受けて金額に納得すれば、代金が振り込まれる
ただし、通貨として使用できる日本の旧紙幣は、現金書留以外の方法で送ることができません。そのため、宅配買取には注意が必要です。
2.オークションサイト
インターネット上のオークションサイトで旧紙幣・古紙幣を出品すると、多くのコレクターに見てもらえるので、売りやすくなります。価格の決め方は、価格を決めて即決で売る方法と、オークション形式で売る方法の2種類です。
また、オークションサイトでは専門家に査定してもらうわけではないため、思ったより高く売れないことや、予想より安値で落札されることがあります。さらに、落札者とのやり取りに手間がかかるうえ、いたずら入札や未払いのリスクもあるため、注意が必要です。
3.フリマアプリ
フリマアプリもオークションサイトと同様に、インターネット上で手軽に売却できる方法です。オークションサイトでは入札期間が終わるまで待つ必要がありますが、フリマアプリでは購入者がいればすぐに取引できます。ただし、手間やリスクはオークションサイトとあまり変わらないでしょう。
4.銀行(両替)
銀行などの金融機関では、古いお札のなかで通貨として使用できる旧紙幣の交換が可能です。ただし、厳密には売買ではなく「両替」と呼ばれます。つまり、旧紙幣の額面どおりと同じ価値で新しいお札と交換されます。
ただし、額面よりも高い価値がある場合、両替すると損をしてしまうことがあるので、気を付けましょう。また、両替には手数料がかかるケースがあり、結果的に額面よりも少ない金額を受け取る可能性もあります。
旧札を少しでも高く売るポイント

旧札は少しの工夫で査定額が大きく変わることがあります。特に以下のポイントを押さえることで、高額買取につながる可能性が高まります。
- 保存状態を良好に保つ
- 複数の買取業者に査定を依頼する
- 買取実績のある専門店を選ぶ
ここまでの内容とあわせてチェックして、お手持ちの古いお札をなるべく高く売却できる状態にしておきましょう。
1.保存状態を良好に保つ
紙幣の物理的なコンディションの最適な状態の維持は、査定額を最大化する重要な要素です。旧札の価値は保存状態によって10倍以上もの価格差が生じることがあります。
保存状態が買取価格に直結する理由は、コレクター市場では美しい状態の紙幣ほど重宝されるためです。希少性と美観の両方を兼ね備えた紙幣に対してプレミアム価格が支払われます。
具体的な保管のコツとしては、以下3つを意識しましょう。
- 直射日光を避けた涼しく乾燥した場所での保存
- 専用のホルダーやクリアファイルを使用した保護
- 温度や湿度の変化が少ない環境での管理
汗や手垢で変色が発生する場合もあるため手で直接触れるのは避け、必要な場合はピンセットや手袋を使用しましょう。
ただし、すでに劣化が見られる紙幣でも価値を持つ場合が多いため、状態が悪いからといって諦める必要はありません。
また、素人判断での清拭や修復は逆効果となる可能性があるため、現状のままでの専門家への相談をおすすめします。
2.複数の買取業者に査定を依頼する
一社のみの査定に依存せず、複数の買取業者から見積もりを取ることは、適正な市場価格を把握し最高額での売却を実現するための重要な工夫です。業者によって専門分野や在庫状況、販売ルートが異なるため、同じ旧札でも査定額に大きな差が生じることは珍しくありません。
各業者の得意分野や市場ネットワークの違いにより、特定の紙幣に対して高い評価をする業者が存在します。複数の業者に査定を依頼すれば、そのような業者を見つけられるのです。
また、競合他社の存在を意識した査定額の提示により、より競争力のある価格での買取が期待できます。
効率的な比較査定を行うためには、インターネットの一括査定サービスの活用、各業者への同時期での査定依頼、査定結果の詳細な記録と比較分析が有効です。また、出張査定や宅配査定を利用すれば、複数業者との取引を効率的に進められます。
ただし、査定額だけでなく業者の信頼性や取引条件も重要な判断要素となることを忘れてはいけません。極端に高額な査定を提示する業者がいた場合、他にかかる手数料等がないか慎重にチェックしましょう。
まねきやでは最短10分で査定額の概算がわかるLINE査定もご用意しています。キャンセル料や査定量無料で利用できるので、査定依頼の手始めにぜひ利用してみてください。
3.買取実績のある専門店を選ぶ
査定先を選ぶ際は、古銭・旧札に特化した専門知識と豊富な取引経験を持つ買取業者を選択しましょう。紙幣の真の価値を適正に評価してもらい、安心できる取引を実現するために、実績は重要な見極めポイントとなります。
専門店が高額買取を実現できる理由は、古銭市場の動向や相場変動に精通していること、希少な記番号やエラー紙幣などの特殊な価値を見抜く鑑定眼を持っていること、専門的な販売ルートにより適正な市場価格での売却が可能なことなどです。後悔しないよう、業者選びは慎重におこないましょう。
まずはインターネットで実績や評価、口コミをチェックして査定料・キャンセル料が無料の業者に査定依頼をしてみるのがおすすめです。その後、査定時の説明が詳細で丁寧か、質問に対して専門的な回答ができるかなど、査定額とあわせて判断しましょう。
なお、専門店を名乗っていても実際の知識や経験が不足している業者も存在します。最終的には査定額と信頼性の両面を総合的に判断し、満足いく売却を実現できる業者を選びましょう。
まとめ
旧紙幣・古紙幣のなかには、思いがけないほど高い価値が付くものがあります。特に希少性の高いお札、記念的なお札、ほかにも限定的なお札やエラーのあるお札などは、高額で取引されやすいです。
また、旧紙幣・古紙幣を売る方法はいくつかありますが、専門の買取業者ならその価値を正しく査定してくれます。
今すぐ売るつもりはなくても、お手もとの旧紙幣・古紙幣を査定してもらい、適正な価値を知っておくとよいでしょう。査定額に満足した場合は、その場で売ることもできます。

この記事の監修者
水野 政行 | 株式会社水野 代表取締役社長
高価買取専門店 まねきや 最高責任者・鑑定士
今まで 54,750点以上の査定実績。
金・貴金属・宝石全般、ロレックスなどのブランド時計、ブランド品全般、切手、古銭、絵画、骨董品全般の査定を得意とする。
2021年より自社ブランドである「高価買取専門店 まねきや」をリリースし、全国に展開。
「売るはめぐる」をコンセプトにした、買取専門店である当店を一人でも多くの方に体感していただくために、私の約15年間の業界経験の全てを注ぎたいと思っております。

 0120-213-213
0120-213-213